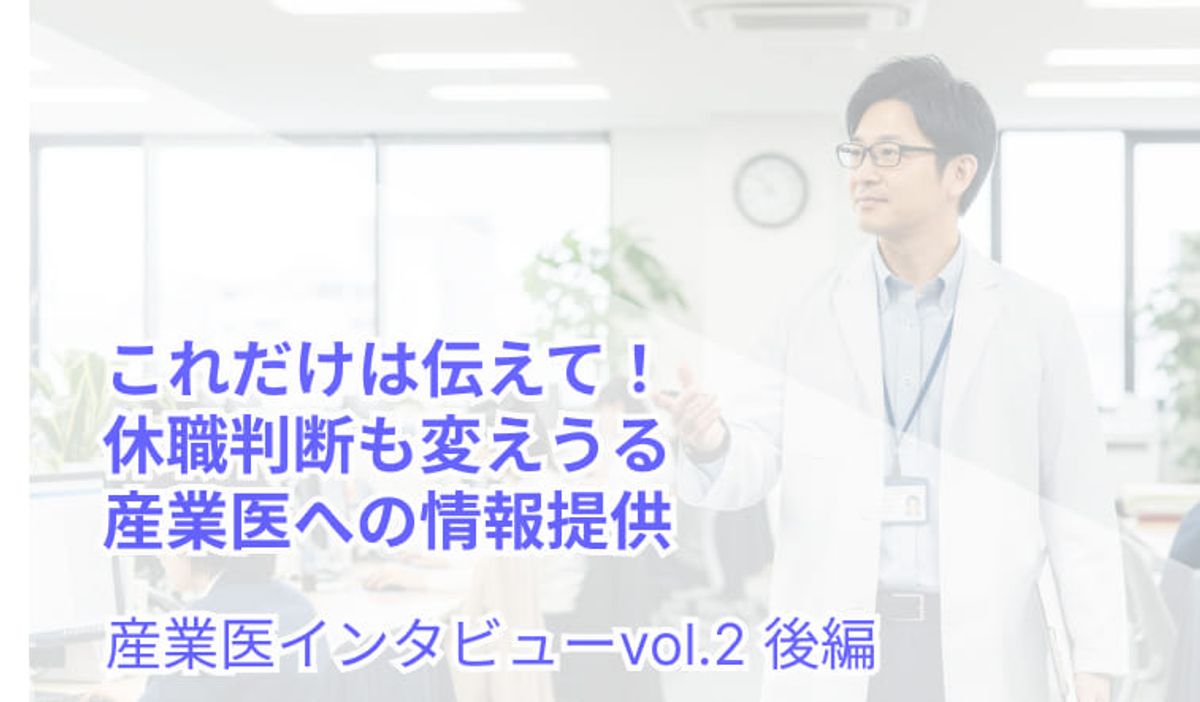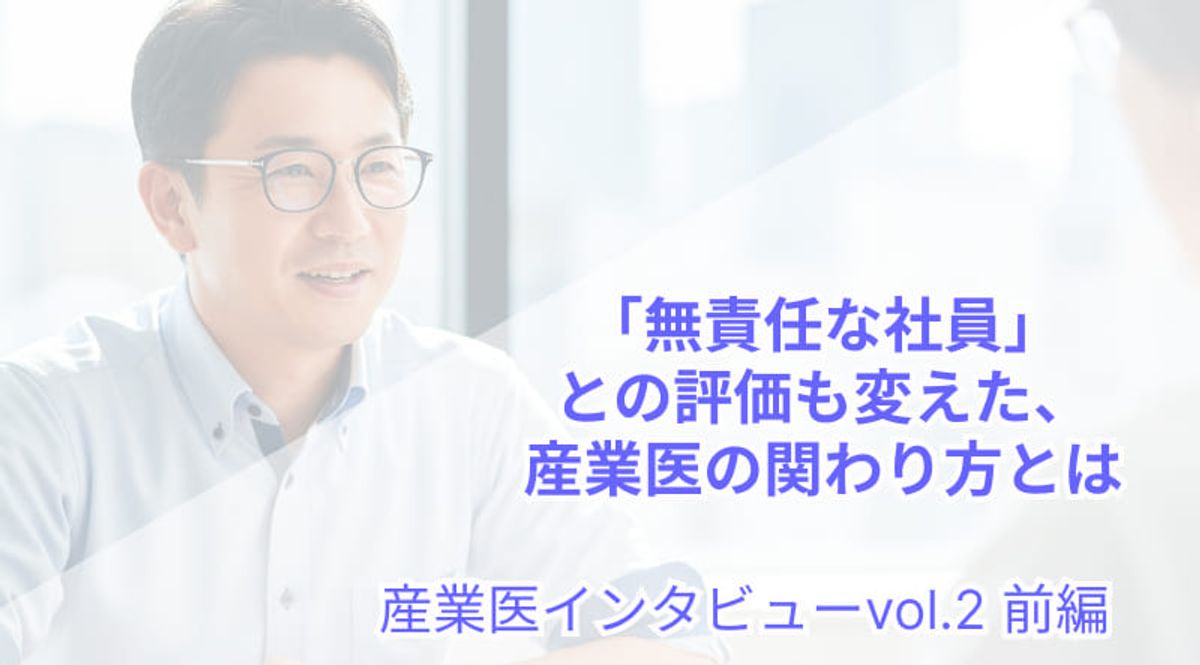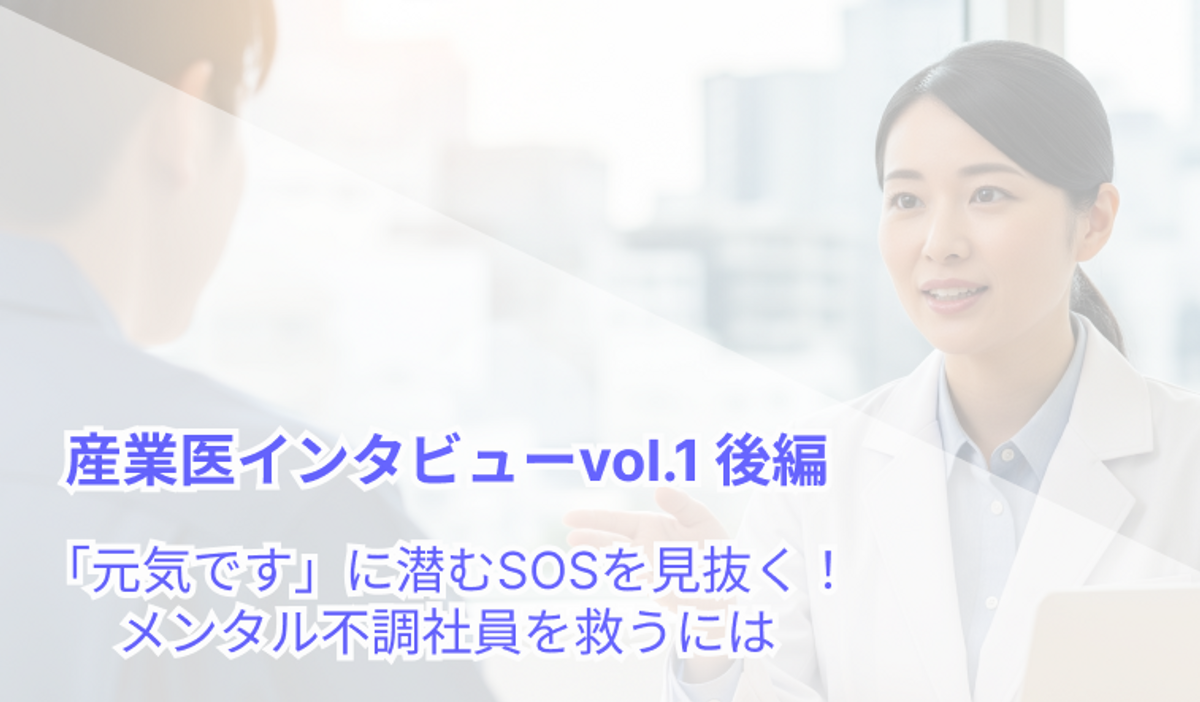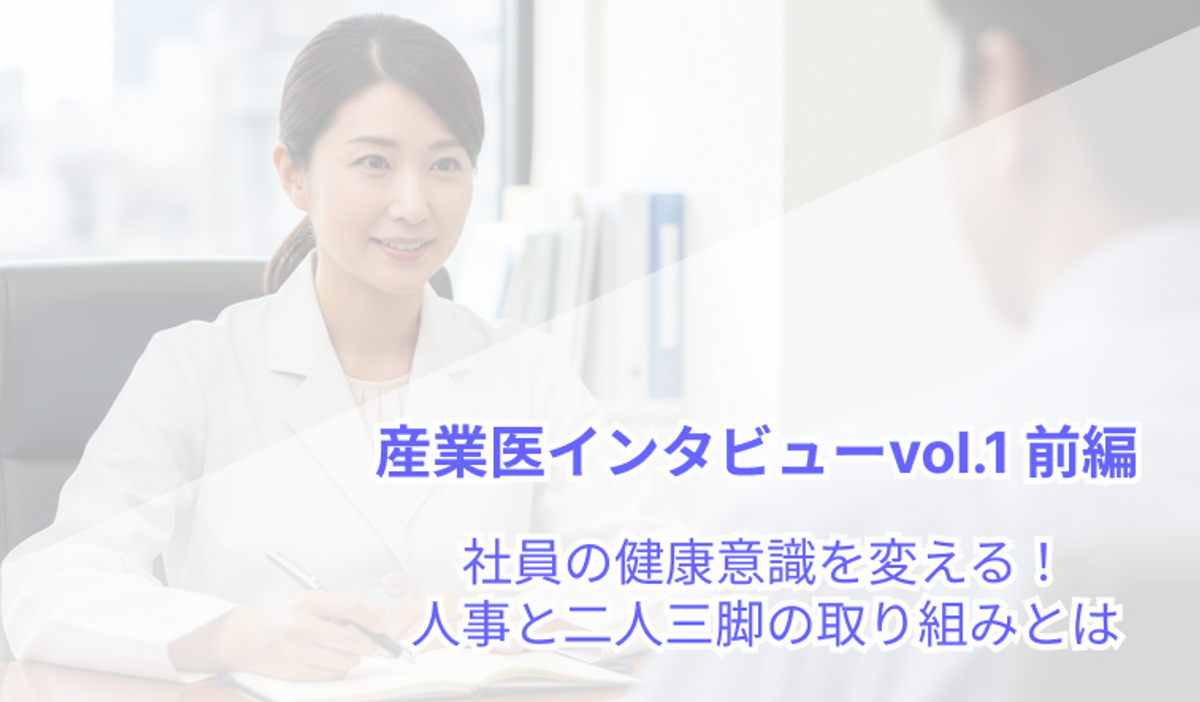地域医療
地域医療について紹介します-
事例
ジェネラリストと中規模病院の価値観を高めるために。ある家庭医の施策―大杉泰弘氏
在宅療養支援病院が皆無だった愛知県豊田市。2015年、市内の豊田地域医療センターに一人の家庭医が赴任したことで在宅医療看取り率が大きく向上しました。年間看取り数120名の在宅医療支援センターを立ち上げる一方で、2018年現在、18名が在籍する総合診療プログラムも構築しています。この状況を作り上げた家庭医・大杉泰弘氏には、ある展望がありました。

-
事例
研究と臨床を行き来して思う、大都市型プライマリ・ケアの役割―密山要用氏
家庭医を志し、王子生協病院で7年半研さんを積んできた密山要用氏。診療を続けていくほどに課題を感じるようになり、行き詰まりを感じた密山氏は、ある決断をしました。今のキャリアを歩む決断に至るまでの悩みや思い、そして今後の展望とは――。

-
事例
都市部の“かかりつけ医難民”を救え!地域に寄り添う家庭医の想い―杉谷真季氏
開業医であった祖父の姿を見て、医師を目指した杉谷真季氏。高校生の時から家庭医を志し、都市部の患者を診ていきたいという明確なビジョンを持ちながら研さんを積んできました。キャリアを築くにあたっての考え方、これから家庭医として取り組んでいきたいことを取材しました。

-
事例
コワーキングスペースを回診! 地域にコミットするクリニックの想い―麻植ホルム正之氏
医療者側から医療の門を狭めない――。麻植ホルム正之氏は、このような思いから2017年9月長野県茅野市にライフクリニック蓼科を開業し、患者に多様な選択肢を提供しています。「人を医療を地域からハッピーに」というビジョンの裏には、どのような思いが込められているのでしょうか。

-
事例
医師を離島医療に掻き立てた“一本の電話”―石橋興介氏
2015年、竹富診療所に赴任した石橋興介氏は、島の人の健康に危機感を覚え、住民と一緒に島の健康づくりを推進。その取り組みが評価され、竹富診療所は厚生労働省主催「第6回 健康寿命をのばそう!アワード」の生活習慣病予防分野で、厚生労働大臣最優秀賞を受賞しました。

-
事例
2人の子持ち医師が、あえて通勤2時間の病院で働くわけ―斎藤舞子氏
祖父の死をきっかけに無医村を知り、地域医療を志した斎藤舞子氏。初期研修を通じて理想の医師像と出会い、医療資源の少ない地域で医師として働く決意を固めます。それを実現するために選んだ勤務先は、自宅から片道約2時間かかる東埼玉病院。斎藤氏の原動力、そして、地域医療にかける思いとは―。

-
事例
医療支援に行った医師が、地域の伝統行事に打ち込む理由―小鷹昌明氏
東日本大震災の翌年、大学准教授を辞め、南相馬市立総合病院の神経内科医として赴任した小鷹昌明氏。医療支援ということもあり、赴任当初は1~2年で南相馬市を離れるだろうと考えていたものの、「医療支援だけではだめだ」と気付き、コミュニティの再構築に奔走します。小鷹先生が赴任して丸6年が経過した今、南相馬市にはどのような変化が生まれたのでしょうか。

-
事例
医師23年目。臨床を離れて学校をつくった医師の再挑戦とは―小栗哲久氏
長年臨床現場から離れていた小栗哲久氏。離島医療を経験後、ホスピスで終末期医療や心のケアに取り組み、2012年には仲間と共に自由な教育方針を掲げた学校を開校させました。医師23年目の挑戦の裏には、どのような思いがあるのでしょうか。

-
事例
近畿地方の子どもたちを守る! 救急集中治療科再編の軌跡―黒澤寛史氏
国内に小児専門の集中治療科がなかった2000年代前半。重症の小児患者への治療に疑問を感じていた黒澤寛史氏は、その思いを原点に小児集中治療医としてのキャリアを歩み始めました。2016年には、兵庫県立こども病院の救急集中治療科の再編に参画。小児集中治療科が最大限の力を発揮できる体制を構築しました。そんな黒澤氏が思い描く、次なる目標とは一。

-
事例
「1年寄り道したっていい」女医のわたしが子連れで高知に単身赴任する理由―桐谷知美氏
理想とする医師像に近づくため、子どもを連れて1年間、高知県宿毛市への単身赴任を決めた桐谷知美氏。その背景には、自身の苦い経験と周囲の後押しがありました。これまで東京都内の急性期病院に勤務してきた桐谷氏が、地域医療に飛び込むことを決意した経緯を取材しました。

-
事例
フットケア専門の訪問診療が必要だ! 地域の声に応えた医師の挑戦―木下幹雄氏
2017年4月、東京都昭島市に、国内では珍しいフットケア専門の訪問診療所を開業した木下幹雄氏。これまで杏林大学医学部付属病院、東京西徳洲会病院にも、難治性潰瘍のフットケア外来を立ち上げてきた木下氏には、形成外科医として地域で実現したいことがあります。

-
事例
北海道岩見沢市・旭川市のまちづくりを「ささえる医療」―永森克志氏
2007年に財政破綻し、市立病院が閉鎖した北海道夕張市で、医療を再建した立役者の一人である永森克志氏。地域医療に興味を持ったきっかけは「自然が美しい地域で医療をしたかったから」と話す永森氏は、現在、北海道岩見沢市でコミュニティドクターとして活躍されています。これまでのキャリアと想いを取材しました。

-
事例
チーム医療を再構築! 感染症多職種チームが自走するまでの軌跡―笠井正志氏
小児感染症専門の臨床医としてキャリアを積んできた笠井正志氏。2016年4月、長年の目標であった感染症科を兵庫県立こども病院に立ち上げました。赴任当時、チーム医療の土台がない状態から、感染症対策の多職種チームが自走できるまでに育て上げた舞台裏に迫ります。

-
事例
年の半分はオンコール、片道数時間の通院患者…若手医師が北海道で見た衝撃とは―齋藤宏章氏
これまで縁もゆかりもなかった北海道北見市で、医師としてのキャリアをスタートさせた齋藤宏章氏。地元である福岡県、大学時代を過ごした東京都とは全く異なる環境を選んだからこそ見えたもの、研修を通じて変わった将来への展望について伺いました。

-
事例
研究者から地域医療研修の教官へ 年間40名超の研修医を魅了する理由―中桶了太氏
離島ながらも、本土と橋でつながっているがゆえに、公的な離島医療支援を受けられていない長崎県平戸市。ここには現在年間40名を超える初期研修医が地域医療研修を受けるためにやって来ます。その立役者は基礎医学研究者から地域医療研修の教官となった中桶了太氏です。

-
事例
医療資源は豊富でも在宅は未整備…12年目の医師が挑む「コミュニティクリニック構想」―今立俊輔氏
父の背中を見て何でも診られる医師を目指した今立俊輔氏。離島医療を経験したのち、医師12年目で選んだ道は、父の運営する今立内科クリニック(福岡県久留米市)での在宅医療部門の立ち上げでした。医師のキャリアとしては比較的早期に実家のクリニックへ戻ろうと考えた、その道に至るまでの思いを取材しました。

-
事例
開かれたコミュニティを生んだ、地域包括ケアの「柏モデル」―平野清氏
地域包括ケアシステムの先進例「柏モデル」で知られる千葉県柏市。この地で、地域包括ケア従事者のコミュニティづくりに一役買っているのが、平野清先生です。先代から60年以上にわたって外来と在宅医療に取り組みつつ、行政や医師会といった組織の力も生かして、医師に負担が偏らない仕組みを作り上げてきました。今回は2009年から取り組みが始まった「柏モデル」の現状と、次世代に引き継ぎたい平野先生の内なる思いを聞きました。

-
事例
都市部ではできない医療を、岡山県山間部集落で―玉井友里子氏
都市部で家庭医として成長する難しさを感じた玉井友里子氏。「何でも相談に乗れるかかりつけ医」を目指すために選んだ場所は、岡山県美作市でした。現在は、美作市内にある2医療機関で診療をしながら、週1回限定で自宅のある“上山集楽”で診療所を開くワークスタイルをとっています。地域との関わり合い、そして、家庭医としての想いを取材しました。

-
事例
地方創生のモデルに。宮城県大崎市で「異次元」の多職種連携に挑む―大蔵暢氏
総合診療医のロールモデルを探しに、アメリカへ留学した大蔵暢氏。そこで出会った老年医学と多職種連携の在り方に衝撃を受け、宮城県大崎市で留学先での学びを実践し始めました。一地方都市でありながら連携の場には多くの人が集まり、「異次元」の多職種連携を行っているといいます。今回は大蔵氏がアメリカで学んだこと、そしてそこでの学びを生かした多職種連携について聞きました。

-
インタビュー
地域包括ケアをわかりやすく 充実度の数値化から見えてくるもの―安藤高朗氏
2025年に向けて整備が進む「地域包括ケアシステム」。その概念は徐々に浸透しつつある一方、抽象的な話で留まっている地域もあります。そのような中で「地域包括ケアインディケーター」という指標を用いて、地域包括ケアの充実度を数値で評価する取り組みを模索しているのが医療法人社団永生会(東京都八王子市)です。今回は安藤高朗理事長に、現在行っている具体的な取り組みと今後押さえておくべき地域包括ケアの指標について聞きました。