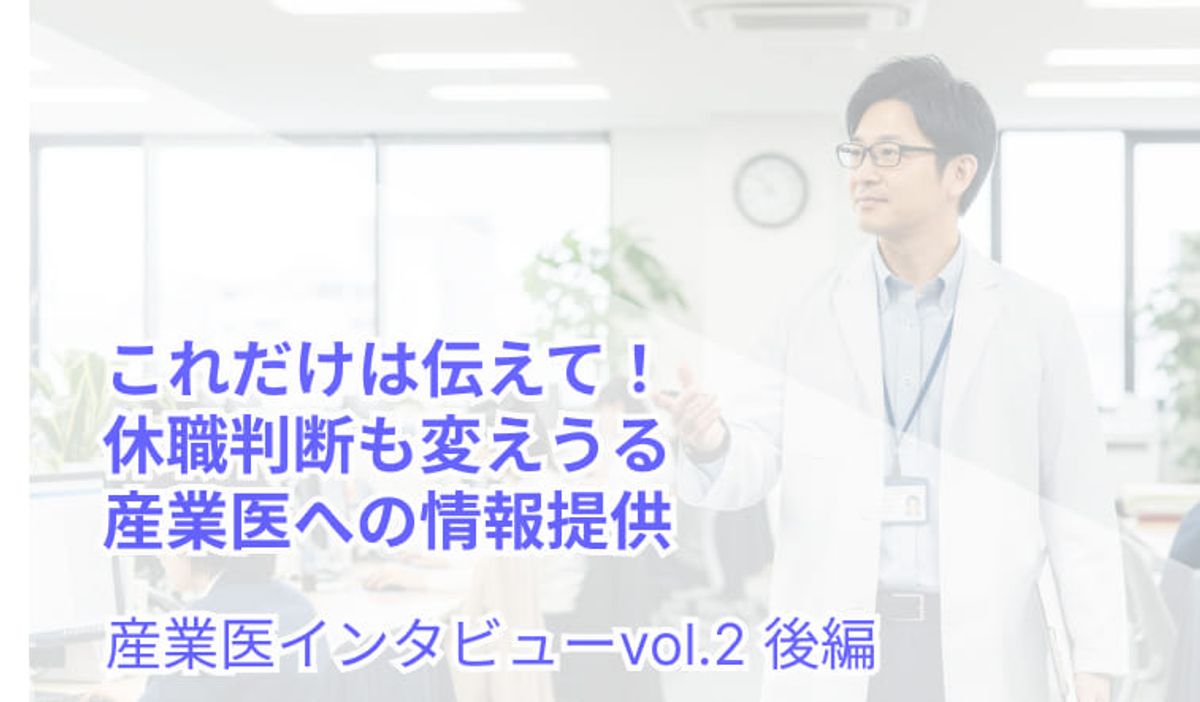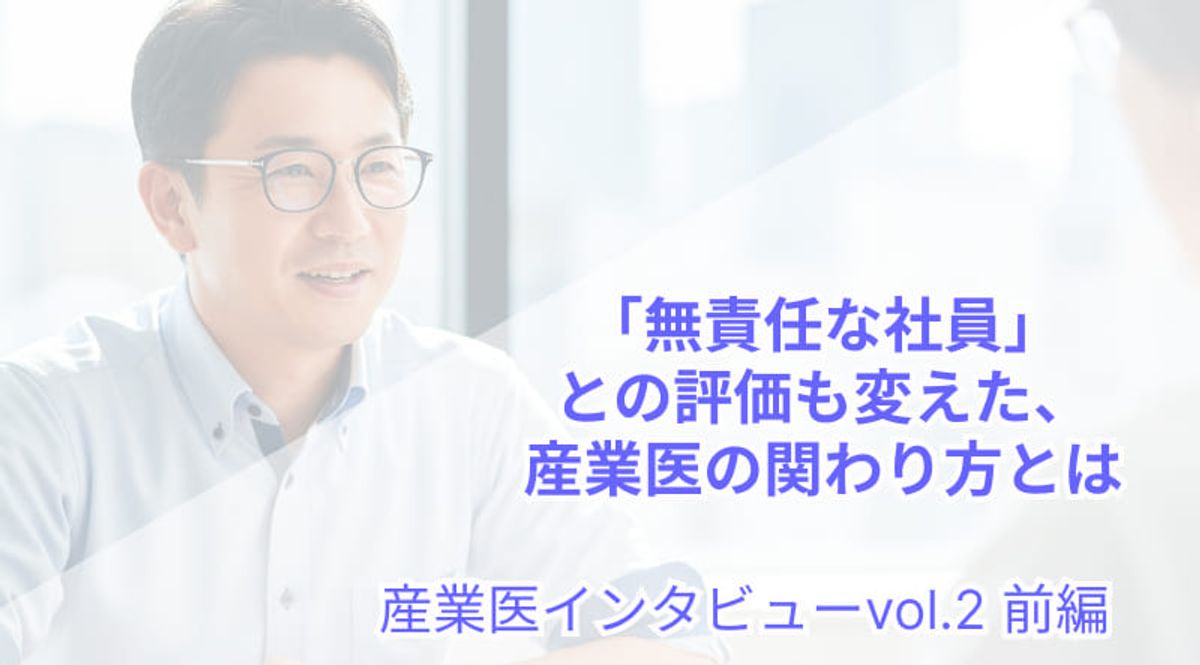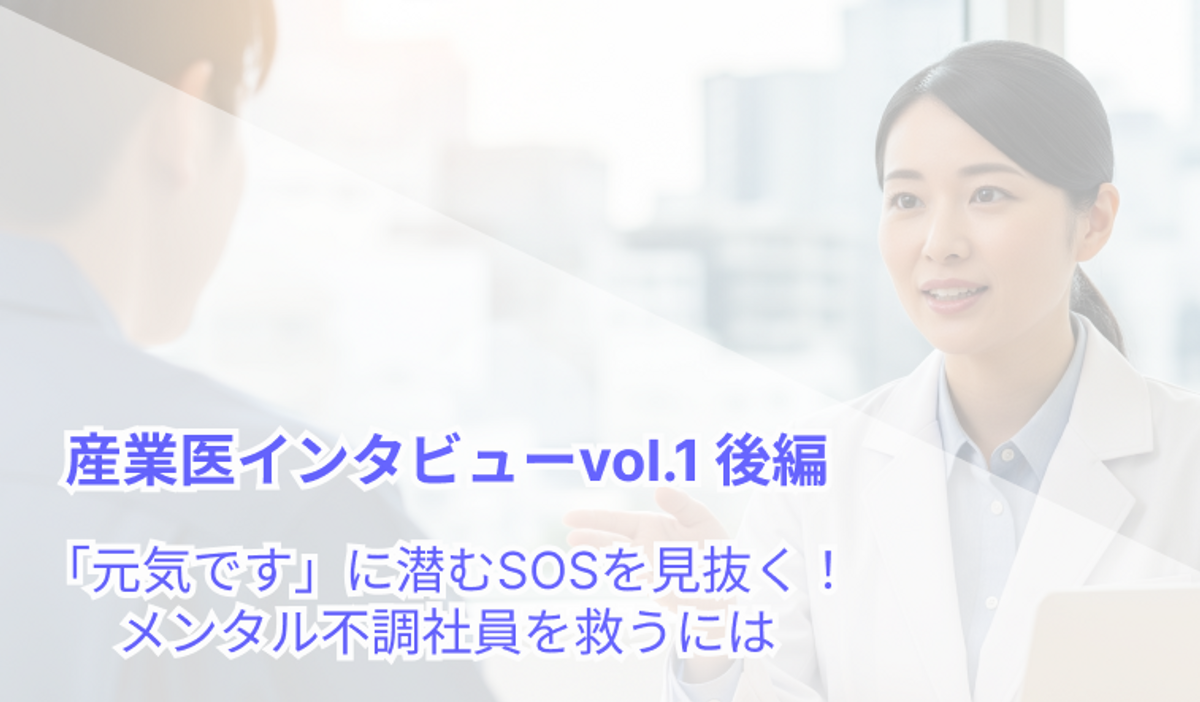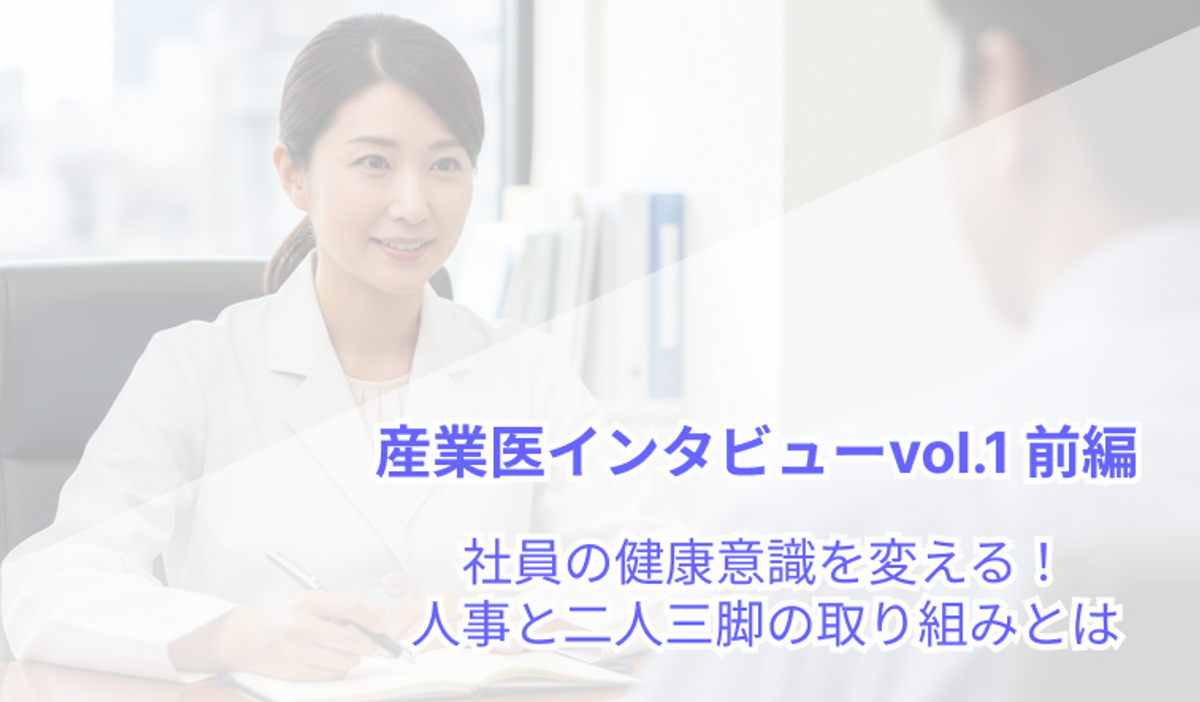地域医療
地域医療について紹介します-
事例
医科×歯科の成功モデルを Wライセンス医師の野望―松本朋弘氏
歯科医師として再生医療の研究に関わったことから、医師免許の取得を決意した松本朋弘氏。現在は総合診療科で内科専攻医として研鑽を積みながら、歯科と医科のダブルライセンスを活かした活動も始めています。

-
事例
一人の町医者が、感染症予備校を14年間主催し続けるわけ―永田理希氏
毎回、全国から多くの方が参加者する感染症の勉強会「感染症倶楽部」。この発起人であるのが、北陸の石川県加賀市で開業している、頭頸部外科・耳鼻咽喉科医の永田理希氏です。なぜ一人の町医者が感染症勉強会を主催するのか――? その背景には、永田氏の立場だからこそ伝えたい想いがありました。

-
事例
医療的ケア児とその家族のために 医師10年目の挑戦―押谷知明氏
小児循環器内科の専門研修を修了後、NPO法人ジャパンハート長期ボランティアに参加した押谷知明氏。帰国後は同科のスペシャリストとしてさらなる研鑽を積むのかと思いきや、プライマリケア医へと方向転換しました。約半年間悩んで出したキャリア転換という答えの背景には、ある思いがありました。

-
事例
“専門医”では表現しきれない「田舎のホスピタリスト」を目指して―海透優太氏
「田舎のホスピタリスト」という耳慣れないキャリアパスの確立を目指し、現在は若狭高浜病院にて研修医教育に力を注いでいます。高浜町の医師になるという夢を叶えた海透氏に、キャリア形成時の悩みと、これからのさらなる目標について取材しました。

-
事例
医師12年目で独立 住民とともに住民主体のケアを―奥知久氏
家庭医療の後期研修プログラムを受けながらも「家庭医と呼ばれたくなかった」と語る奥知久氏。ある時を境に、自らの役割を見出し、家庭医の道を歩むことを決意します。そして2019年4月、9年勤めた病院を退職。フリーランスの医師として、コミュニティケアの活動に取り組もうと考えた理由とは――。

-
事例
「小児総合診療科」を根付かせるために―利根川尚也氏
志していた外科から一転、小児総合診療科への道を選んだ利根川尚也氏。広い視野を持ち、体系的に医療を提供したいという思いを胸に後期研修を迎えたものの、現場で感じたのは「日本での小児総合診療科の立ち位置の曖昧さ」でした。そして今、その曖昧さをなくすために、さまざまな取り組みを実践しています。

-
事例
チーフレジデントが「医療を変える」―長崎一哉氏
医師5年目でチーフレジデントを務めたことで、その後のキャリアに大きな変化があった長崎一哉氏。現在は、日本チーフレジデント協会設立に向けて準備を進めています。この取り組みについて、「医師人生をかけてやる価値がある」と語る長崎氏に、キャリアチェンジの背景、今後の展望について取材しました。

-
事例
「仕事も子育ても及第点」 2児のママが医長と育児を両立できる理由―本郷舞依氏
坂総合病院(宮城県塩釜市)で総合診療科の医長を務める本郷舞依氏は、2児の子育てをしながら働くことに「常に悩み、ワークライフバランスは不安定」と言います。それでも総合診療の最前線で働き続けているのは、困っている人からの求めに応え続けるため。そのために救急科とタッグを組むなどの職場環境を築いています。今回は本郷氏を支える原動力と、仕事と子育てとを両立する術について聞きました。

-
事例
医師不足地域でも複数医師体制を継続できる施策とは―坂戸慶一郎氏
健生黒石診療所(青森県黒石市)では、複数医師体制の継続に注力しています。その背景には、所長を務める坂戸慶一郎氏の「病院の負担を減らし、地域全体の医療をしっかり支えていきたい」という考えがありました。坂戸氏が思い描く理想の診療所像、今後の展望についてお話を伺いました。

-
事例
フリーランス医師が、県知事を志すまで―川島実氏
京都大学医学部在学中にボクシングのプロライセンスを取得し、29歳まで約5年間プロボクサーとして活躍してきた川島実氏。その間に医師免許を取得し、ボクサー引退後は、医師として全国各地の医療機関に勤務してきました。東日本大震災後は、被災し院長不在となった気仙沼市立本吉病院(宮城県)の院長に就任。2014年に院長を辞任した後は、地元・奈良県に戻ってきました。型にはまらないキャリアの持ち主である川島氏のその後を追いました。

-
事例
診療科の方針転換 若手医師の思惑とは―森川暢氏
医師7年目に東京城東病院総合内科(現・総合診療科)のチーフとして、診療現場の責任者となった森川暢氏。診療科の方針転換をはかり、総合内科と家庭医療を融合させた総合診療科を目指す意図や今後の展望を伺いました。

-
事例
地元・福島県で家庭医育成に力を注ぐ理由―菅家智史氏
医師4年目で母校・福島県立医科大学に戻り、家庭医として福島県山間部で研鑽を積み、現在は教育に携わっている菅家智史氏。菅家氏が教育に注力する理由とは――。

-
事例
平日23時まで開院することに決めた理由―嘉村洋志氏・瀬田宏哉氏
東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科で出会った嘉村洋志氏と瀬田宏哉氏は、共通の課題感を持ち、共同代表という形式をとって、2018年4月にロコクリニック中目黒(東京都目黒区)を開院しました。救急現場から地域医療へ目を向け、軸足を移した2人の想いとは――。

-
事例
医療×公民館?! 市民巻き込み型の緩和ケアを推進する理由―横山太郎氏
神奈川県横浜市で緩和ケア医としての診療の傍ら、現代版公民館「Co-Minkan」を始めた横山太郎氏。一見、医療とは縁遠い公民館。横山先生に「Co-Minkan」を立ち上げた理由、今後の展望について伺いました。

-
事例
総合診療の学び舎を 岩手の窮状を見てきた医師の挑戦―山田哲也氏
大学卒業後から一貫して岩手県内の医療に携わり、県内の窮状を何度も目の当たりにしてきた山田哲也氏。そんな山田氏は、2018年5月から岩手医科大学救急・災害・総合医学講座 総合診療医学分野の助教に就任し、新たな挑戦を始めています。これまでどのような想いを持って、キャリアを歩んできたのかを取材しました。

-
事例
病院のブランドには頼らない! キャリア形成を3軸で試みる医師―中山祐次郎氏
中山祐次郎氏は卒後10年間、都内の有名病院にて外科医として研さんを積み、高度な手術も担ってきました。2017年、葛藤を感じながらも、福島県郡山市の総合南東北病院への赴任を決意。そんな中山氏の目指すこととは――?

-
事例
約3時間かけて、宮城県松島町へ遠距離通勤する理由―小松亮氏
2015年、家庭医の小松亮氏は一念発起して自宅は東京のまま、宮城県松島町にある松島海岸診療所で勤務することを決意しました。このようなワークスタイルを選んだその背景には、どのような想いがあったのでしょうか。

-
事例
「緩和ケアはコンビニであるべき」常勤医7名体制の緩和ケア科の挑戦―柏木秀行氏
医師5年目に、総合診療科から緩和ケア科に転籍した柏木秀行氏。現在は緩和ケア科部長として若手を中心とした6名の医師を束ね、緩和ケアの新たな価値を提供しようとしています。若手医師が集まる理由、そして緩和ケアの新たな価値とは――。

-
事例
地元の医療を支えるために。家庭医が追求したもう1つの専門性―遠井敬大氏
埼玉県出身の遠井敬大氏は、父の姿に憧れ家庭医という道を選択しました。医師5年目から診療所の所長を務め、家庭医としての研さんを積んできましたが、10年目には救急科での勤務を始めました。このようなキャリアを選択した遠井氏の考えとは――。

-
事例
住民が身近な離島医療 親しさゆえのジレンマとは―張耀明氏
家庭医の張耀明氏は長年、へき地医療に携わりたいと考えていました。2017年、そんな張氏に東京都・新島へ赴任するチャンスが到来します。2018年度からは診療所長も務める張氏に、新島の医療事情や課題、将来の展望について率直に語っていただきました。