
吉野 聡(よしの・さとし)
2003年3月 筑波大学医学専門学群卒業。精神科病院で研修後、東京都知事部局精神科健康管理医、筑波大学医学医療系助教を経て、2012年に吉野聡産業医事務所を開設。医学と法務の2つの博士号を持ち、労働者のメンタルヘルスと関連法規が専門。2017年には、産業医の枠を越えて、企業のリスクを軽減し、職場を成長させるメンタルヘルス対策の立案と実践を主軸業務とする、ゲートウェイコンサルティング株式会社を創業。精神科専門医・指導医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)の資格を活用し、大企業からスタートアップ企業まで、多くの職場のメンタルヘルス対策に従事している。
職場復帰の際に従業員から出された部署異動の希望に関しては、頭を悩ませている会社も少なくないと思われます。
職場復帰の際に従業員から出された部署異動の希望に関しては、頭を悩ませている会社も少なくないと思われます。
職場環境によるストレスが原因でメンタルヘルス不調に陥った場合、同じ環境に戻しても、また再発してしまうのではないかという心配と、メンタル不調から回復したばかりの社員を受け入れる職場を社内で見付けることが出来るのかという懸念とが、その判断を難しくします。
連載第3回となる今回は、復職時に出された異動の希望と、職場に求められる対応について紹介したいと思います。
診断書に記載された「部署異動」。安易な対応にご注意
先月号の『突然提出された療養が必要とする診断書をどう考え、どう対応するか』
で取り上げた通り、メンタルヘルス関連の診断書には、本人の希望が強く反映されていることが一般的ですから、「職場復帰時には異動・配置転換等の配慮が望ましい」といった記載がある診断書が提出されることはしばしばです。しかし、会社の人事施策は、事業の全体最適を目指す取り組みですので、個々人の希望や嗜好性が必ずしも優先される訳ではありません。
しかも、本人の希望が盛り込まれた診断書を元に安易に職場(以下、「部署」の意を含みます)異動ができてしまうと、「嫌な職場に配属されたら、メンタルクリニックに行って、異動が必要な診断書をもらってくればよい」という、誤った認識が社員の中に広がってしまうおそれがあります。
さらに、それにより自分が希望していない職場で必死に頑張っている社員のモチベーションを大きく低下させてしまうこともあります。
「まずは元の職場への復帰」の原則の是非
厚生労働省の「改訂版 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」には、以下の記載があり、職場復帰に関しては、「まずは元の職場への復帰」で対応すべきとされています。
(以下、手引きからの抜粋です)
ア「まずは元の職場への復帰」の原則 職場復帰に関しては元の職場(休職が始まったときの職場)へ復帰させることが多い。これは、たとえより好ましい職場への配置転換や異動であったとしても、新しい環境への適応にそれはやはりある程度の時間と心理的負担を要するためであり、そこで生じた負担が疾患 の再燃・再発に結びつく可能性が指摘されているからである。これらのことから、職場復帰に関しては「まずは元の職場への復帰」を原則とし、今後配置転換や異動が必要と思われる事例においても、まずは元の慣れた職場で、ある程度のペースがつかめるまで業務負担を軽減しながら経過を観察し、その上で配置転換や異動を考慮した方がよい場合が多いと考えられる。(後略) 出典:厚生労働省「改訂版 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
(以上、手引きからの抜粋です)
この原則には様々な意見があるものの、現場産業医(筆者)の感覚としては、合理的だと感じています。
それは、手引きに記載されている通り「復帰する社員への配慮」という一面もありますが、組織運営上もその様にせざるを得ない側面があるように思うからです。
実際には、メンタル不調で休職していた社員が職場に復帰する際、その社員を快く受け入れる部署を見つけることが難しいという課題があります。
現場で想定される事態と合理的な配慮を考える
社内を見渡せば、人手が欲しいと感じている職場は見付けられると思います。しかし、その様な職場においても、欲しい人材は元気にバリバリ働いてくれる人材であることがほとんどで、回復後間もない社員のニーズはほとんどないのが現状です。
特に、メンタル不調からの復職者の場合、「安定した勤務ができるのだろうか?」「うちの部署でもうまく適応できないのは?」「ストレスがかかったら、また具合が悪くなってしまうのでは?」という懸念があるため、受け入れに懸念を示す職場が大半といえるでしょう。
また、運よくそのような職場が見付けられたとしても、それには「公平性・平等性」という重要な原則が付きまといます。
つまり、メンタル不調からの復職時、誰かに異動の配慮を行ったら、他の労働者からも同様の申し出があった時には、同じように対応する必要があるという基本原則です。
ここで人事担当者の好き嫌いで、受け入れの際の配慮に差が出てしまうことはあってはなりません。重要な基本原則ではあるものの、このような事態が複数発生した際に、そのたびに異動先を見付けることは至難の業といえます。
また、コミュニケーション手段が多様化し発達している現代においては、休職している社員同士のコミュニティが形成されていることも少なくなく、「○○さんは復職時に異動できたらしい」という情報はすぐに回ってしまうため、企業の対応をより難しくしている側面もあります。
このように、新しい職場への適応にも一定のストレスがかかることに関する労働者側への配慮と、メンタルヘルス不調者の異動を簡単には考えられない会社側の事情を勘案すると、まずは元の職場に復帰し、安定した勤怠や着実な職務遂行能力の発揮を確認した後、必要に応じた異動の検討、という対応を原則にすることが合理的だといえるのです。
会社は全体の健康を考えた復職の制度設計を行うべき
実際に職場復帰時にどの程度の配慮を行うのかは、会社全体の健康度を向上させる施策として考えるべきだと思います。
私の産業医先の企業の中にも、復職時の制度では「職場復帰時の配慮は、主治医・産業医の医学的な意見も含めて柔軟に対応する」とする会社もあれば、「週5日、1日8時間、元の職場で就労できることを職場復帰の条件とする」とする会社もあります。
また、その中間型として、「原則、元の職場での復帰を求めるが、短時間勤務からの段階的な職場復帰を認める」という会社もあります。
これらの復職に関する制度設計は、それぞれ一長一短があり、完璧な制度は存在しません。
そもそも、復職に関する問題は、単に健康に関する安全配慮の問題だけでなく、会社がどのような労務提供を受領するのかという労働契約の問題も含んでいるため、自分の会社の風土・文化も踏まえ、会社の課題を解決するための制度を慎重に検討する必要があります。
労働契約を厳密に解釈して、職場復帰時に全く配慮をしない(=給与に見合った労務提供ができるようになるまで復職を認めず、その様な状態になるまでは休職とする)ことも一案です。
しかし、誰もがメンタル不調になる可能性があるストレス社会の現代において、一生懸命仕事をして、無理をしてしまった結果としてメンタル不調になっても、「会社は復職時に全く配慮をしてくれないのだ」と従業員が感じてしまえば、その様な会社で長く働こうというモチベーションは毀損されることになるでしょう。
その一方で、復帰時の診断書に配慮事項を書いてもらえれば、リモート勤務などの柔軟な働き方や、本人が希望する部署での就労が許容されるとなってしまうと、やりたくない仕事でも、会社のために必死に頑張って出勤している労働者の就労意欲が低下してしまうことになってしまいます。
ですので、自分の会社において、メンタル不調に陥った労働者に対する個別問題の解決という観点だけでなく、元気にモチベーション高く働く労働者の健康度も含め、会社全体の健康度を向上させる取り組みとして、制度を検討することが、現場を見てきた産業医としては適切だと考えています。
産業医としてのキャリアをご検討中の先生へ

エムスリーキャリアでは産業医専門の部署も設けて、産業医サービスを提供しています。
「産業医の実務経験がない」
「常勤で産業医をやりながら臨床の外勤をしたい」
「キャリアチェンジをしたいが、企業で働くイメージが持てない」
など、産業医として働くことに、不安や悩みをお持ちの先生もいらっしゃるかもしれません。
エムスリーキャリアには、企業への転職に精通したコンサルタントも在籍しています。企業で働くことのメリットやデメリットをしっかりお伝えし、先生がより良いキャリアを選択できるよう、多面的にサポートいたします。
.png?1763605558?w=120)








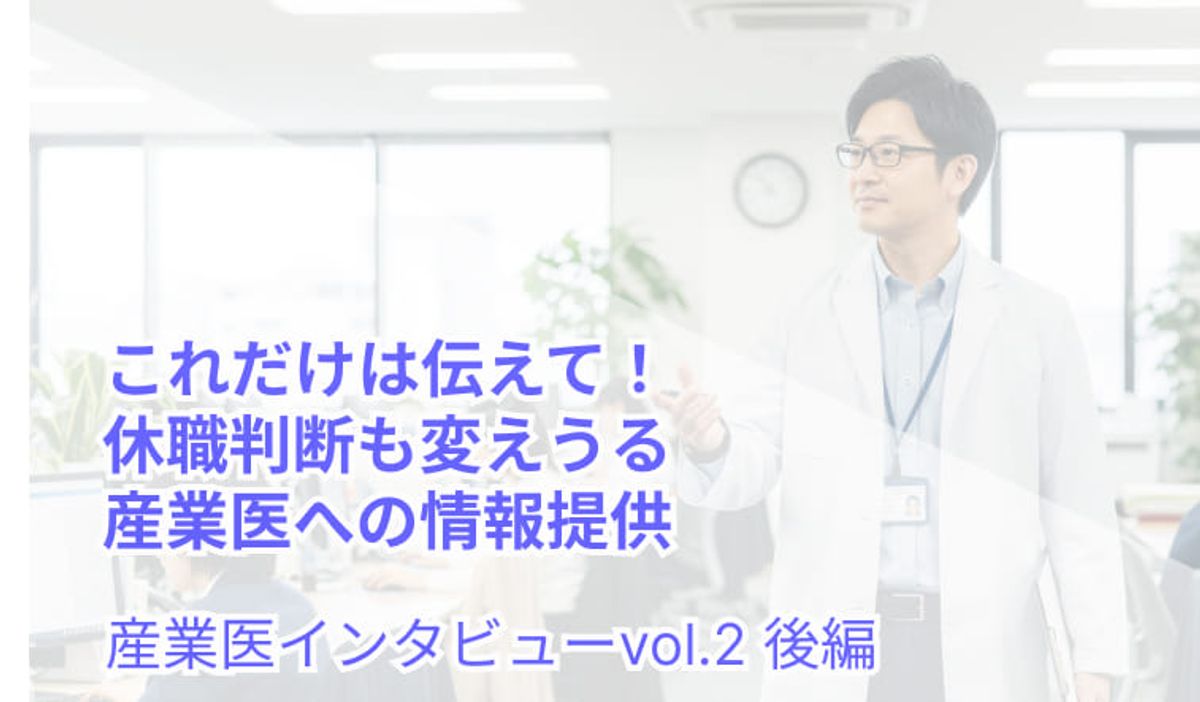
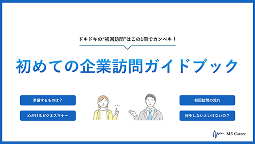
.png?1730779856?w=96)
.png?1763605558?w=96)






