
吉野 聡(よしの・さとし)
2003年3月 筑波大学医学専門学群卒業。精神科病院で研修後、東京都知事部局精神科健康管理医、筑波大学医学医療系助教を経て、2012年に吉野聡産業医事務所を開設。医学と法務の2つの博士号を持ち、労働者のメンタルヘルスと関連法規が専門。2017年には、産業医の枠を越えて、企業のリスクを軽減し、職場を成長させるメンタルヘルス対策の立案と実践を主軸業務とする、ゲートウェイコンサルティング株式会社を創業。精神科専門医・指導医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)の資格を活用し、大企業からスタートアップ企業まで、多くの職場のメンタルヘルス対策に従事している。
突然提出された療養が必要とする診断書をどう考え、どう対応するか
最近、医師の発行する診断書、特にメンタル不調に関連する診断書への社会的信頼が大きく低下しているのではないかと感じさせる状況が発生しています。
都内のとあるメンタルクリニックが、公式サイトで「通院不要、お薬の処方は不可、診断書の即日発行」などを掲げたことで大炎上したこともありました。
これに限らず、実際にインターネットでメンタルクリニックを検索すると、検索上位に来るクリニックのほとんどに『診断書即日発行』の文字が並び、医療機関が診断書発行をビジネスとして行っているのではないかと感じさせる状況を目の当たりにします。
私が産業医として仕事をしていても、職場の人事担当者からは、「普通に働いていた社員が、上司から叱責された翌日に突然、メンタル不調の診断書を持参して、休みに入ってしまった」など、診断書が水戸黄門の印籠(ちょっと表現が古いですが……)のような機能を果たしている事態を見聞きします。
客観的な検査データに乏しいメンタル不調の場合、職場や産業医は診断書が唯一の医学的所見となることも多く、「本当に病気なのかな?」と腑に落ちないまま、対応を進めなければならない事態に遭遇することも少なくないと思われます。
今回は、こうした診断書の発行を取り巻く現状と、職場で求められる対応について書きたいと思います。
診断書の即日発行は医学的に正しいのか
メンタルクリニックを初めて受診したその場で、療養が必要な旨の診断書が出ることに違和感を覚える方もいるかと思います。この点に関しては、「診断書を発行することで患者さんの健康を守らなければならない場合もあるので、一概に否定されるべきものではない」という回答が正しいように思います。
診断は、医師が患者さんを診察して病状を判断する行為を指しますから、必ずしも病名を特定する必要はありません。
ですから、患者さんが、非常に強い気分の落ち込みや出社をすることへの不安を抱いている場合などは、病名や治療法をじっくり検討する前に、まずは緊急避難的に会社を休ませることが必要だと判断することは、十分に合意的な話です。
もちろん、そこまで精神的な健康状態が悪化をしているのであれば、会社と相談をして、休暇をもらうなどの対応をすればよいのではと思いますが、実際に多くの会社において、傷病に関する休暇・休職制度を利用する際には、診断書の提出を要件としていることが多いことも事実です。
また、一見して健康問題が分かりやすい外傷や緊急性が明白な脳・心臓疾患などと異なり、メンタル不調の場合に自らの健康状態の悪化を証明する手立てとして、診断書を提出しなければ休めない、と考える労働者の心理にも配慮が必要です。
さらに、職場におけるメンタル不調の多くが、職場内の人間関係に起因しているため、自らの体調不良について上司や人事に相談することすら難しく、その結果、メンタルクリニックに駆け込み、会社を休むための診断書を入手するという手段を取らざるを得ない労働者が一定割合存在すると思われます。
信頼できる医療機関はなかなか予約が取れない現状
このような状況の中で、メンタルクリニックの予約の取りにくさが問題となることも少なくありません。実際に、患者さんとの対話によって病気の診断と治療を目指す精神科医療においては、他の診療科目よりも診察時間が長くなってしまい、一日に診察できる患者数にも限りがあります。
ですから、ネット上での評判の良いクリニックや地域で信頼されている医療機関などは、2~3週間から1か月以上先の新患予約しか取れないという状況は日常茶飯事です。
しかし、実際に会社で強いストレスを抱えて、明日、会社に行くこともつらいと感じている労働者にとって、そんなに長い期間、診療が受けられない状態を我慢しながら、日々を過ごすことは非常に強い苦痛となってしまいます。
そんな時、インターネットでメンタルクリニックを検索すると、「今日行ける」「当日受診OK」「毎日夜10時まで診療」「土日も診療」「休職診断書、当日発行」などの欲しかった文字が目に飛び込んできます。もちろん、このようなフレーズを掲げている医療機関の大半は医師としての使命感をもって取り組まれていることを理解している一方で、都心部を中心に精神科のトレーニングも十分に受けていない医師が、患者さんの希望に応じた診断書を発行しているようなケースも残念ながら散見されます。
そのようなケースの中には、「診断書になんと書いておきますか?」「薬は必要ですか?」と医師から尋ねられたという事例も少なくなく、専門職としての矜持を失ってしまっているのではないかとがっかりすることも少なくありません。
つまり、信頼できる医療機関の予約はなかなか取得が難しく、すぐに予約が取得できる医療機関の中には、医療と呼ぶことすら憚られるような質の低い医療を提供している機関が存在する現実があるのです。
医師の職業倫理と精神科医療の特性が生み出す診断書の妙
そもそも、患者さんの希望通りの診断書を発行することが、医療と呼べるのでしょうか?これに関しては医師の職業倫理と精神科医療の特性を踏まえて考える必要があります。
1981年に採択された、『患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言』の序文には、「医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきである」と書かれており、『医師の職業倫理指針(日本医師会 第3版 平成28年)』にも、「医師は患者の利益を第一とし、患者の権利を尊重し、これを擁護するように努めなければならない。」と記載されています。通常、診療に従事する医師は、患者さんの利益を守り、権利を擁護するために行動することが正しい行動であると教育されているのです。
また、実際に職場におけるメンタル不調の中では、様々な要因から職場不適応を起こしている事例が多く、その様な事例においては職場から離れることが健康状態の回復につながることがほとんどです。
つまり、「最近、職場でストレスが溜まって辛いんです。明日から仕事に行きたくないんです」という患者さんが目の前に現れた時、その方の希望通りに療養が必要な旨の診断書を発行することが、医師の倫理観としても、精神科医療としても正しい行為と位置付けられることが多いのです。
突然、メンタル不調の診断書提出があった時、職場ではどのように対応すべきか
ある日突然、メンタル不調で療養が必要な旨の診断書を持参して、休みたいと言われた場合の職場の対応について整理をしておきましょう。
基本的には、職場での就労に関する診断書は、本人の意思に反して交付されることは考えにくいと言えます。
一定程度金銭的な負担が発生する診断書ですから、患者さんが明確に「診断書は不要です」と言っているのに、医師の側で無理やり発行するケースは想定しにくいです。
また、医療機関で発行された診断書が会社に提出されるにプロセスの中には、必ず労働者が提出するという行為が介在するため、多少の迷いがあることはあっても、おおむね労働者としても休むことを希望していると考えることが妥当でしょう。
中には、「本当に病気なのか?」「休まなければいけないほど具合が悪いのか?」などと疑問を唱える上司や人事の方もいますが、上述の通り基本的には休みを申し出た労働者本人も休みを希望しているケースがほとんどですし、医師が病気で休みが必要だと言っている状況に対し、「病気ではない」「休みは必要ない」ことを証明するのは、悪魔の証明のようなものですので、その点を争う合理性は乏しく、可及的速やかに休めるように段取りを進めることが適切といえます。
この場面において、診断書を受領したら、即日休ませなければいけないのか、職場側からすると、最低限の引継ぎ期間すら許容されないのか、という質問を受けることが良くあります。ここに関しては、診断書を提出した労働者が、安心して療養に専念できる環境を確保するという観点で話を進めることが適切です。
真面目に責任感をもって仕事に取り組んできた労働者の場合、全く何の引継ぎもせずに即日休むように指示されても、同僚のこと、取引先のこと、既にスケジュールされているアポイントメントのこと、自分が不在の間のメール対応のことなど、様々なことが心配で、安心して休むことが困難と考えられます。
ですから、数日間(通常は2~3日、長くても1週間程度)の引継ぎ期間を設けることで、安心して療養に入ってもらうことができるのであれば、労働者本人が即日休みに入ることを希望している場合や、自殺念慮があるなど病状が深刻な場合を除けば、労働者と合意の上で、最低限度の引継ぎ期間を設けることは許容されると考えられます。
もちろん、この場合でも、できるだけ引継ぎを短期間で済ませることや、リモート対応が可能であれば、在宅等の安心できる環境で引継ぎ対応してもらうなど、精神的負荷を軽減する配慮は重要です。
あらためて職場のメンタルヘルス対策を見直す
また、取り急ぎの対応が終わった後は、なぜ突然、メンタル不調で療養が必要な旨の診断書が提出されるような事態が発生してしまったのか、一度、社内のメンタルヘルス対策について見直す機会とするとよいでしょう。
よほど大きな精神的ストレスが生じない限り、ある日突然メンタル不調になるという事態は考えにくく、メンタルヘルス対策がうまく機能していれば、診断書の提出の前に、体調や職場でのストレスなどについての相談が、上司、人事、産業医等に上がってくるはずです 。
最近は事前の相談や調整もなく、いきなり第三者が退職手続きを仲介する退職代行の利用なども話題になることありますが、日頃からの職場内の円滑なコミュニケーションや安心して相談できる体制が不足していると、今回お話をしてきたような、突然の診断書提出に至ってしまうことが見られます。
産業医の立場では、このような事象が発生した際には、産業医の存在が職場でしっかりと認知されているか、産業医に安心して相談できる体制が構築されているか、ラインケア教育などを通じて職場のメンタルヘルス対策が周知徹底されているか、などを再点検する機会とすることが望ましいといえます。
.png?1763605558?w=120)








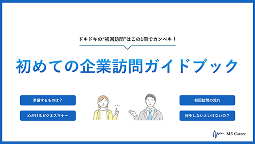
.png?1763605558?w=96)







