
吉野 聡(よしの・さとし)
2003年3月 筑波大学医学専門学群卒業。精神科病院で研修後、東京都知事部局精神科健康管理医、筑波大学医学医療系助教を経て、2012年に吉野聡産業医事務所を開設。医学と法務の2つの博士号を持ち、労働者のメンタルヘルスと関連法規が専門。2017年には、産業医の枠を越えて、企業のリスクを軽減し、職場を成長させるメンタルヘルス対策の立案と実践を主軸業務とする、ゲートウェイコンサルティング株式会社を創業。精神科専門医・指導医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)の資格を活用し、大企業からスタートアップ企業まで、多くの職場のメンタルヘルス対策に従事している。
制度導入から10年。ストレスチェックの「マンネリ化」が課題に
2015年12月から始まったストレスチェックも今年で制度導入から10年を迎えます。
制度導入当初は、産業医の中でも「メンタルヘルスには自信がないから実施者を引き受けたくない」、「自分は精神科医ではないから、高ストレス者の面接指導はできない」などと、様々な不安の声が聞かれました。
また、事業所も「どのストレスチェックシステムを導入するか」など、産業保健業界ではストレスチェックの話題で持ちきりでした。
しかし、最近では、産業医の不安な声も聞かれなくなり、事業所からは「最近ストレスチェックがマンネリ化してきて、受検率が下がってきました。どのような工夫が考えられるでしょうか?」といった新たな課題が指摘されるようになってきています。
また、労働者からも「毎年同じような質問で、どうせ、今年も高ストレス判定だよ」、「こんな無意味な回答に時間を使うくらいなら、その分、早く帰れた方がストレスが減るよ」と、ストレスチェックに対して否定的な発言も目立ち始めています。
2024年5月に3年以内にストレスチェック制度が中小企業にも義務化される法案が成立するなど、ストレスチェック制度は当面継続されることが間違いない中、その価値や有効性が危ぶまれ、方策の見直しが必要な転換期に、産業医や人事担当者はどのように向き合えばよいのでしょうか?
企業と産業医が模索するストレスチェックの「脱マンネリ化」
このような事態に対して、「これまでは57項目の標準的な質問紙を用いてきたが、今後は80項目ないし120項目の充実した質問紙に変更して、労働者にもより役立つストレスチェックに変えていきましょう」といった助言をする産業医の声を耳にすることが少なくありません。
確かに標準とされている57項目の質問紙と比べ質問項目が増えれば、ワークエンゲージメントなど、ポジティブメンタルヘルスに関するアウトプットなども期待でき、マンネリ化解消の一つのアイデアとは成り得るでしょう。
また、最近、メンタルヘルスとの結びつきが強いとされる心理的安全性や、健康経営において重要な指標となるプレゼンティーズムなどもストレスチェックの枠組みで測定する事業所も増えてきていますので、ストレスチェックに新たな視点を盛り込むという効果は期待できると思います。
ただ、私はこのような、質問項目を追加し、目新しいアウトプットを求めることは、この先、数年間の新鮮さをもたらすだけで、ストレスチェック制度のマンネリ化に対する根本的な対応になるとは考えていません。
このマンネリ化問題に正面から向き合うには、「なぜ、ストレスチェック制度が職場にも労働者にも期待されなくなってしまっているのか」という根本的な問題に目を向ける必要があります。
それは、端的に言えば、ストレスチェック結果が十分に活用されておらず、ストレスチェックに時間をかけて回答するメリットを労働者が享受できていないことに他ならないのではないでしょうか?
ストレスチェックの本質は「一次予防」ということを意識する
ストレスチェックの一番の目的は、二次予防を目的とした健康診断と異なり、一次予防の充実であったはずです。
特に、集団分析結果から事業所が職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、働きやすい職場づくりを促進させることがこの制度の一番の目的であり、メンタルヘルス問題の発症予防段階である一次予防の充実が図られることが期待されていたわけです。
しかしながら、集団分析を実施している事業場は8割程度、実際に職場環境改善に取り組んでいる事業場は50%台で推移を しています。
つまり、半分近くの事業場では、ストレスチェックを実施しても、職場環境改善にはつながっておらず、「ストレスチェックをやったことで、働きやすい職場になった」と労働者が実感することが無い状態になってしまっているのです。
当然のことながら、健康診断では自覚していない異常が検査で見つかる可能性があります。しかし、ストレスチェックは自記式の回答ですので、自分で記入している最中に、「ああ、今年は高ストレスと判定されそうだ」、「こうやって回答しておけば、面接指導の対象にはならないはずだ」などと自らの結果を想像することもできます。
ですから、1年に1回、自らのストレス状況を認識する機会を提供するという意味合いはあっても、自覚と全く異なる驚きの結果となり、「受検しておいてよかった!」などという事態は発生しにくいのです。
そうなると、受検する労働者が個人で享受できるメリットはそれほど大きなものではなく、受検しても職場も何も変わらない、もしくは変わっていてもそれを実感できないのであれば、徐々にこのストレスチェック制度は形骸化していってしまうのです。
誤った職場環境改善の実行は逆効果
集団分析結果に基づく職場環境改善においても、あまり効果的ではないばかりか、ストレスチェックへのモチベーションを下げたり、正直な回答を妨げたりする結果になっている取り組みも散見され、注意が必要です。
例えば、高ストレス職場への介入と称して、総合健康リスク120以上の職場の管理職だけを集めて、職場環境改善プランを作成させるような取組を目にしたことがありますが、これは個人的には非常に悪手だと感じました。
高ストレス職場の上司の大半は、自分の職場の仲間が強いストレスを感じながら働いていることを理解しており、何とかしなければと考えています。
分かっているけれど、どうにもできずに悩んでいるのに、その上司に、高ストレス職場から脱却するための方策を考えさせても、付け焼き刃的に紋切り型の施策しか出てくるわけがありません。そのようなことに時間を使うのであれば、少しでも職場で部下の話を聞く時間に回した方が、ましなはずです。
高ストレス職場は、管理職のマネジメントスタイルの影響が強い場合もありますが、それ以外にも会社の構造的な問題であることも少なくありません。
上流工程の仕事が遅れがちで、最終的に帳尻を合わせなければならない下流工程の職場で裁量権を奪われてしまっていたり、現場重視の考え方が強すぎて間接部門へのリソースが不足しがちであったり、他部署でストレス過多となり体調を崩した労働者が集められているような職場でモチベーションの維持が難しかったりと、高ストレスとなる要因は様々です。
どこの部署が高ストレス職場なのかを、より具体的に特定したい、などの目的で集団分析の単位を(個人が特定されない範囲で)小さく区切ることを選択する事業場も増えてきている印象がありますが、これも必ずしも効果的な取り組みとは言えません。集団分析の単位を小さくすればするほど、高ストレス部署の特定には役に立つかもしれませんが、分析人数が小さくなれば、個々人の結果の影響が強く出てしまうため、集団としての分析結果の価値が毀損されてしまいます。
高ストレス職場を特定することが目的な訳ではなく、働きやすい職場づくりにつなげることが目的な訳ですから、(個人ではなく)集団の分析として意味ある結果を得ることが重要です。そのため、分析単位は小さくても10-20名程度が適切でしょう。
集団分析結果の活用が効果を生み出している事業場の共通点
では、どのような集団分析結果の活用が望ましいのでしょうか?
それはもちろん、絶対的な正解がある話ではありませんが、事業所の雰囲気や風土、様々なストレス要因や健康課題などを目にしている産業医だからこそできる提案があるのではないでしょうか。
まさに産業医の知恵の絞りどころ、腕の見せ所といえるところです。
私が多くの事業場で産業医を務めている経験上、集団分析の活用が上手くいっている事業場の特徴としては、共通して以下の3点が挙げられます。
- 集団分析結果がオープンになっていること
- (高ストレス職場に限定せず)事業場全体で取り組んでいること
- 多くの労働者が参画する取り組みであること
つまり、集団分析の結果を、ごく限られた一部の人しか閲覧できないような状態では、労働者は自分たちの職場の実態を知らされていない訳ですから、改善のしようがありません。
また、高ストレス職場の問題を、その職場だけの問題に終わらせず、会社全体で、皆で取り組んでいくという姿勢が無ければ、本当の意味での職場環境改善にはつながりません。
産業医として支援した職場環境改善の好事例
最後に一つ、私が産業医としてストレスチェック結果の職場環境改善の取組を支援させて頂いた中で、うまくいった事例をご紹介させて頂きます。
その事業所は、高ストレス職場が発生している状況を事業所全体の問題と捉え、高ストレス職場への支援策を、高ストレスではなかった各職場から1つ以上考案して、実行してもらうという施策を実施しました。
それまでは、「高ストレス職場ということが他の部署に知られることは不名誉であり、恥ずかしい」という意識や、「高ストレス職場であることを部署のメンバーが知ったら、皆、他の部署に異動願を出してしまうのではないか」という不安があり、高ストレス職場の改善策を職場の管理職だけで考えていました。
しかし、3年連続で同じ職場が高ストレス職場となってしまったことをきっかけに、総括安全衛生管理者である事業所長から産業医に相談があり、前記のような施策実施に至りました。
そうしたところ、「繁忙期には応援で人を出す」、「繁忙期に業務が集中しないように、生産計画を再考する」といった、具体的な業務改善案から、「高ストレス職場の職員と昼食を一緒にとり、愚痴を聞く」、「休憩時間ように差し入れをする」などの情緒的な対応まで職場ごとに色々な施策が創出され、会社全体で高ストレス職場を支援しようという雰囲気が醸成されるようになりました。
このように、労働者が「ストレスチェックに答えることで、自分たちの職場が良くなった」と感じられることこそが、本当の意味でのマンネリ化対策になるのではないかと私は考えています。
厚生労働省が出している
には、ストレスチェックの基本的な考え方から、有効な事例まで、数多くの情報がまとめられていますので、是非これらの情報を参考に、職場に合った取り組みを考えてみてください。産業医としてのキャリアをご検討中の先生へ

エムスリーキャリアでは産業医専門の部署も設けて、産業医サービスを提供しています。
「産業医の実務経験がない」
「常勤で産業医をやりながら臨床の外勤をしたい」
「キャリアチェンジをしたいが、企業で働くイメージが持てない」
など、産業医として働くことに、不安や悩みをお持ちの先生もいらっしゃるかもしれません。
エムスリーキャリアには、企業への転職に精通したコンサルタントも在籍しています。企業で働くことのメリットやデメリットをしっかりお伝えし、先生がより良いキャリアを選択できるよう、多面的にサポートいたします。
.png?1763605558?w=120)








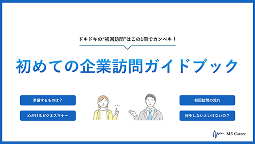
.png?1763605558?w=96)







