産業医の業務を行う上で、活動の根幹となるものが「労働衛生の3管理」です。 本記事では「労働衛生の3管理」の概要について紹介しています。従業員の安全と健康を守るため、産業医が取り組むべき基本的な柱となりますので、この機会に再確認しておきましょう。
労働衛生の3管理とは

労働衛生の3管理とは「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」の3つのことを指します(これに「総括管理」「労働衛生教育」を加えて5管理と呼ぶこともあります)。 これら3つの管理は、それぞれが独立して行われるだけでなく、互いに密接に連携することで、労働者の健康を守るために機能します。
産業保健専門職の倫理綱領作業環境管理
作業環境管理は、物理的因子、化学的因子、生物学的因子など有害な作業環境因子を排除または低減することで、快適な職場を維持するための管理です。
産業医の役割は、作業環境測定結果を評価し、それをもとに改善策への助言や新たな設備の導入、作業プロセスの変更に介入することです。
勤務先が一般的なオフィスの場合で物質を取り合わないような場合であっても、空調や照度などを適切に管理することが求められます。
なお、作業環境測定を行うべき作業場は労働安全衛生法施行令 第21条にて定められています。
作業管理
作業管理とは、作業の方法や手順を適切化することです。従業員が安全かつ健康的に作業できるよう、産業医は労災防止の観点等から改善に向けた介入をします。
具体的な方法としては、作業標準(作業手順書の作成・周知等)の確立や作業時間・休憩時間の管理、保護具の使用徹底、ヒューマンエラー対策(KYTトレーニング)などがあります。
産業医は、作業内容・作業負荷の評価と作業方法の改善提案などを行う他、長時間労働者には面談を実施し、健康障害の防止に努めます。
健康管理
健康管理は、従業員の健康状態を把握し、早期に健康障害の発見と対策を図ることです。
健康診断の結果に基づいて、保健指導の実施や再検査の受診勧奨を行います。また、労働者からの健康相談に対応することも産業医の役割です。
ストレスチェックも同様に、高ストレス判定が出た場合は、従業員からの申し出により面接指導を行います。 また、従業員のヘルスリテラシーを向上させるために労働衛生教育を実施します。その際には、労働災害防止だけでなく、安全配慮義務、自己保健義務(労働者が自身の安全・健康管理に務める義務)があることを伝えます。まとめ
「労働衛生の3管理」を実践することは従業員の健康と安全を守る上で不可欠です。個別具体の対応も大切ですが、産業医として職場の環境全体を視野に入れたアプローチをすることが求められますので、必ず身につけておきましょう。
.png?1763605558?w=120)








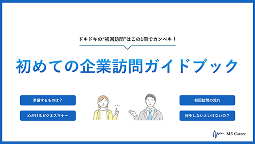
.png?1763605558?w=96)







