
現在20社の嘱託産業医を務める産業医・古河 涼先生に、企業と産業医の連携について伺った今回のインタビュー。後編では、具体的にどのような情報を産業医に提供すると産業保健がうまくいくのか掘り下げていきます。 ※本稿は、人事労務担当者向けの記事を一部編集して掲載しています。
.jpg?1756359307)
|
公衆衛生分野の研究に従事後、産業医として活動。5年間で幅広い業種・規模の企業を担当。これまでに製造業(食品、事務用品、自動車)、鉄道業、IT業界、金融業、コンサルティング業などの企業で、従業員の健康管理、メンタルヘルス対策、職場環境改善などに尽力してきた。 現在は嘱託産業医として20社と契約し、専門的な立場から企業の産業保健をサポートしている。 |
産業医とうまく連携するための情報提供、なにから始める?
――従業員の健康問題、特に休職者が出た場合、見落としがちな点があるそうですね。
休職者が出た場合、その従業員への対応はもちろん重要ですが、周囲で働く方々への影響にも目を配る必要があります。なぜなら、休職者が抜けた分の業務を肩代わりして、残された従業員が過重労働になってしまうケースが少なくないからです。また、休職者が復職してもすぐに100%のパフォーマンスを発揮できるわけではないため、周囲の負担が一時的に増すこともあります。
さらに、休職者が復職した後も、周囲の従業員が気を遣う必要があり、精神的な負担や気苦労が多くなるケースもあります。特に、リモートワークを積極的に活用している企業では、こうした周囲の従業員の状況が表面化しにくいこともあります。
それから、人は感情でも動きますから、たとえ合理的な休職判断であっても「休職者だけが守られている」と感じ、不満を抱く従業員が出てくることもあります。「あの人が休職したせいで…」といった不満は、なかなか公には言いにくいものです。最近では1on1が広がっているように、人事労務担当者や管理職の方が、積極的に従業員の状況を個別に汲み取れるようなコミュニケーションを心がけることが大切です。産業医としても、面談を通じて職場環境を把握し、必要に応じて企業側に改善提案することで、間接的に周囲の従業員のケアをサポートできると考えています。
――産業医との連携も欠かせませんね。企業と産業医とのコミュニケーションで特に意識すべきことは何ですか?
ぜひ、職場の状況や文化に関する情報、そして従業員の業務内容について、惜しみなく産業医に提供していただきたいです。産業医は、企業の方々が思っている以上に職場の文化や仕事の内容について知りたいと考えています。皆さんの会社では当たり前になっていることも、産業医にとっては貴重な情報となる場合があります。
たとえば就業措置の判断に影響する要素は多く、従業員が行っている仕事の内容、リモートワークの可否、短時間勤務の有無、現在の業務の忙しさなど、挙げるとキリがありません。その中でも見落とされがちなのは「リモート勤務が可能かどうか」です。自宅から2時間かけて満員電車で通勤するのと、完全在宅でリモートワークが可能なのとでは、復職時に求められる健康状態のレベルが大きく異なります。復職面談の前にこうした情報が共有されていないと、産業医の判断が根底から変わってしまうこともあります。
――産業医への情報提供で、押さえておくべきポイントはありますか?
何から伝えればいいかわからないという場合は、厚生労働省の「治療と仕事の両立支援」における「勤務情報提供書」(※)のようなフォーマットも活用し、できるだけ具体的な情報を提供いただけると、より的確な助言が可能になります。
一方で、私たち産業医側も、医師が当たり前だと思っている医学的なことを、一般の方にも分かりやすく伝えることを心がけなければならないと考えています。企業と産業医、お互いにとっての当たり前が、相手にとっては当たり前ではないことを理解し、歩み寄るコミュニケーションが非常に重要だと考えています。
(※)勤務情報提供書(資料内p.5):厚生労働省ウェブサイトで公開されている「治療と仕事の両立支援」に関する書式。企業や従業員が主治医に情報提供する際に活用できる。
――医師にとっての“当たり前”でいうと、従業員の疾患を正確に理解するのに苦労しているという人事労務担当者の声も聞きます。
企業の方からすると、「疾患名を聞いても何のことか分からない」、あるいは「インターネット上に情報があふれていて、何を信じていいか分からない」といった状況に直面することはあるでしょうね。このような時にこそ、産業医を“水先案内人”として活用していただきたいです。
産業医は、そうした疾患について分かりやすくご説明したり、数ある情報の中から信頼できる情報源をご紹介したりすることができます。従業員本人にとっても、企業にとっても、正確な情報を得て、適切な判断を下すことは非常に重要です。
たとえば、従業員が持参した診断書に書かれた病名が、人事労務担当者の方には馴染みが薄いものである場合。インターネットで検索すると、過度に不安を煽るような情報や、誤解を招くような情報も少なくありません。このような時、産業医に相談いただければ、病気の基本的な知識、症状、治療の見通し、職場での配慮事項などを、専門用語を避け、分かりやすい言葉でご説明することができます。
さらに、主治医からの情報が少ない場合や、記載内容が職場の状況と合致しない場合などにも、産業医が主治医との連携を促したり、必要な情報提供を補足したりすることで、より実効性のある就業配慮に繋がります。産業医は、医療の専門家として、正しい情報へのアクセスをサポートし、企業が適切な判断を下すための助けとなることができます。
多分野の専門家への“水先案内人”としての産業医
――一歩進んだ論点として、他の分野の専門家との連携についてお聞かせください。
産業医活動に求められる多種多様な知識に比べると、医学部や医療現場で学んできたことは限られています。そこで、私が今後特に力を入れていきたいと考えているのが、「多分野の専門家との連携」です。
たとえば、法的な論点についてです。就業措置や復職の可否は、医学的なことだけでは決まりません。「元の作業はできないが、別の作業なら可能」という場合、会社が代替業務を用意する義務があるのかどうかは、医学的な論点ではなく法律的な論点です。しかし、医師はそうした労働法に関する専門教育を受けていません。
もちろん、全ての法律をマスターすることは不可能ですが、「これは法律の専門家に相談すべきだ」と判断できる”トリアージ(選別)能力”は身につけていきたいと考えています。従業員の働く権利や会社の義務に関わることは、安易に産業医一人で判断すべきではありません。ですので、企業の方々にお願いしたいのは、産業医から「◯◯に相談してください」と提案があった際には、「たらい回しにされた」とマイナスにとらえず、提案された方への相談を検討していただきたいです。
また、化学物質対策も同様です。近年の労働安全衛生法改正により、化学物質に関するリスクアセスメントなどが強化されました。有害性の判断や作業環境の改善については、専門的な知識が必要です。産業医が全てを抱え込むのではなく、作業環境管理の専門家など、その道の専門家にご協力いただくことが重要だと考えています。
産業医は、単に病気や健康に関する助言をするだけでなく、企業が抱える多様な課題に対して、適切な専門家へと繋ぐ“水先案内人”としての役割も担っていくべきだと考えています。私たち自身も常に学び続け、専門家と連携することで、より質の高い産業保健活動を提供できるよう努力していきます。
前編に戻る
【関連記事】
・社員の健康意識を変える!人事と二人三脚の取り組みとは―産業医インタビューvol.1前編
・「元気です」に潜むSOSを見抜く!メンタル不調社員を救うには―産業医インタビューvol.1後編
産業医としてのキャリアをご検討中の先生へ

エムスリーキャリアでは産業医専門の部署も設けて、産業医サービスを提供しています。
「産業医の実務経験がない」
「常勤で産業医をやりながら臨床の外勤をしたい」
「キャリアチェンジをしたいが、企業で働くイメージが持てない」
エムスリーキャリアには、企業への転職に精通したコンサルタントも在籍しています。企業で働くことのメリットやデメリットをしっかりお伝えし、先生がより良いキャリアを選択できるよう、多面的にサポートいたします。
.png?1763605558?w=120)








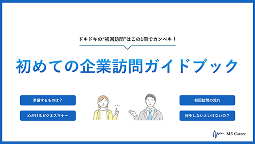
.png?1763605558?w=96)







