
吉野 聡(よしの・さとし)
2003年3月 筑波大学医学専門学群卒業。精神科病院で研修後、東京都知事部局精神科健康管理医、筑波大学医学医療系助教を経て、2012年に吉野聡産業医事務所を開設。医学と法務の2つの博士号を持ち、労働者のメンタルヘルスと関連法規が専門。2017年には、産業医の枠を越えて、企業のリスクを軽減し、職場を成長させるメンタルヘルス対策の立案と実践を主軸業務とする、ゲートウェイコンサルティング株式会社を創業。精神科専門医・指導医、労働衛生コンサルタント(保健衛生)の資格を活用し、大企業からスタートアップ企業まで、多くの職場のメンタルヘルス対策に従事している。
自分の会社の社員がメンタル不調に陥った後、なかなか病状が回復せずに長期の休職に至るケースや、職場復帰をしたものの、あまり病状が改善していると思えず、低調なパフォーマンスが継続する場合などにおいて、通院中の精神科医療機関(本稿では精神科、心療内科、メンタルヘルス科など、心の健康問題を診療の対象とする医療機関を一括して『精神科医療機関』と表記します)への継続的な受診で本当に大丈夫なのか、また、主治医との信頼関係はきちんと構築されているのだろうか、と人事や産業医の立場から心配に思う場面に遭遇します。
そのような時、自分の会社の社員が通っている医療機関やその主治医が本当に信頼できるのか、どのように見極めればよいのでしょうか?
通院先への信頼感と医師選択の自由の尊重
信頼に値する医療機関について考える際、誰にとっても絶対的に信頼できる完璧な医療機関などは存在しないということ、言い換えればどのような医療機関や主治医に信頼を置くかは、人によって価値観が異なるということであり、これを理解しておくことは重要です。
自分の気持ちに寄り添って、自分の希望を最大限に尊重してくれる医師に信頼を置く人もいれば、エビデンスに基づき理論的に助言や指導を行ってくれる医師を信頼する人もいるでしょう。
医療機関の選定においてまず重要なことは、通院治療を受けている社員が、本当に安心し、医師を信頼して受診が出来ているかという点ですので、会社や産業医が権威的に「あの医療機関はダメだ。すぐに転院した方が良い。」などと一方的な対応をすることは好ましくないでしょう。
そもそも、受診先医療機関の選定においては、診療を受ける医師や医療機関を自由に選択できる権利として医師選択の自由が人権上も保証されるべきですので、無理に会社が勧める医療機関への転院を促すことは控えるべきと考えられます。
ただ、これまで何軒ものメンタルクリニックを受診し、その違いが分かるという社員はほとんど存在せず、最初に受診した医療機関での体験により、「精神科医療機関ってこんなもの」と考えてしまっていることも多く、必ずしも治療中の社員さんが、現在通院中の医療機関に全幅の信頼を置いているとも限りません。
そこで、「今、受診している先生を信頼して、なんでも相談できていますか?」と投げかけて頂き、少しでも不安や違和感を抱いているようであれば、人事や産業医として相談に乗ることは適切な対応と言えます。
患者さん全員にとって「いいお医者さん」になることが難しい事情
精神科の医療機関の選定に当たって、「よく話を聞いてくれる先生が良い」、「薬ではなくカウンセリングで治療してくれる先生を希望する」などと、時間をかけてじっくりと対話をすることを望む声を多く聞きます。
もちろん、患者との対話は、客観的な検査指標の乏しい精神科医療においてはとても重要です。
その一方で、国民皆保険制度が充実している我が国においては、保険診療が一般化しており、精神科領域においても、自由診療はまだまだ少数派といえます。
保険診療は、国民が標準的な医療を、安心した価格で受けることには適した制度であると言えますが、診療報酬は国が定める金額に統一されているため、丁寧に長く話を聞いたからと言って、診療報酬が診療時間に比例して高くなることはありません。
少々、雑な言い方になりますが、5分診療で薬を処方するケースと、20分話をじっくり聞いて薬を処方しないケースでは、前者の方が処方箋を発行する分、高額な診療報酬を得ることができるのです。
1人の診療を5~6分程度で行い、1時間で10人の患者さんを診る医師と、1人の診察に20分かけて、1時間で3人の患者さんしか診察できない医師では、得られる診療報酬に3倍以上の開きが出てしまう制度なのです。
もちろん、医療法において、営利目的で医療機関を経営することは禁止されていますので、医療機関が利益追求をすることは論外ですが、医療は寄付等で成り立つ慈善事業でもありません。
医療機関の運営には、人件費や賃料は当然のこと、最近では医療のDX化に対応するために様々なIT機器・システムの購入やリースなどにも相当の費用が発生します。
それに対し、国の高齢化やそれに伴う社会保障費の増大に対応する政策の影響で、物価上昇に応じた診療報酬の改定は期待し難く、むしろ精神科の診療に関する診療報酬は近年、引き下げられている現状があります。
さらに、診療報酬は全国均一の価格ですから、高額な賃料が発生する都心のターミナル駅の近くでは、かなりの数の患者さんを診察しなければ、医療機関が赤字になってしまうことは事実なのです。
ですから、多くの精神科医が、できることなら患者さんの話をじっくり聞いて、その患者さんに向き合って対応したいと考えつつも、医療機関の経営を維持していくという観点からは、保険診療であまり長い診察時間の確保は困難であるというジレンマを抱えているのです。
診療する医師の資格から医療の質を担保する
意外と社会に知られていない事実としては、医師免許を保有している人であれば誰でも「精神科医」と名乗ることができてしまうということです。
精神科医を名乗るには、精神科医としてのトレーニングや経験をしっかりと積まなければいけないと思われている方も多いのですが、医師免許は全ての診療科目に適用できる免許ですので、基本的には医師であれば誰でも精神科医を名乗ったり、精神科医療機関で勤務をしたりすることができます。
また、精神科医療においては身体的侵襲を伴う手術や検査を行うことはほとんどありませんので、専門的なトレーニングを受けていなくても、精神科医っぽい振る舞いをして、診療行為を行うこともできてしまうのです。
そこで、一定のトレーニングと経験を積んでいる医師かどうかを見極める方法として、診療を受けている医師の資格を確認することは、一つのアイデアです。
精神科医療に関する資格としては、「精神保健指定医」と「精神科専門医」の2つが有名です。
「精神保健指定医」は、重度の精神障害を持つ患者の入院、隔離、身体拘束など人権を制約することになる行為に関する判断を下せる資格で、一定の要件を満たした医師が厚生労働大臣から指定を受けます。
「精神科専門医」は、適切な教育を受け、精神科診療において備えるべき専門的診療能力を有し、標準的な医療を提供できる医師として、日本専門医機構が認定する資格です。
これら2つの資格を取得するには、医師として5年の診療経験と、3年以降の精神科診療の実務経験が必須になり、さらに経験しなければいけない症例のレポート提出や、資格の特性に応じた試験に合格しなければならないため、精神科医として一定のスキルと経験を有していることの最低限の証明としてとらえることができます。
もちろん、様々な思想や経緯からこれらの資格を取得せずに診療を行っている優秀な精神科医や、まだ資格取得には至らないものの志をもって真剣に精神科診療に向き合っている若き精神科医もいますし、逆にこれらの資格を有していても、残念ながら診療に熱心ではない精神科医もいますので、一概に資格だけで判断することは難しいですが、一つの参考材料としてはわかりやすのではないかと思います。
なお、自分が診療を受けている医師が、精神科専門医かどうかは、公益財団法人日本精神神経学会のHPから検索することも可能 ですので、お試しください。
メンタルヘルス対策における正解は一つではない
職場のメンタルヘルス対策を考える上では、メンタルヘルス不調者が発生しないような予防的な取り組みが最も重要と考えられますが、ストレス社会と呼ばれる昨今の状況を考えると、「自分の職場の社員が、不調に陥ってしまったら、どのような医療機関を勧めたらよいのか」という視点も、人事担当者や産業医にとって、必要不可欠な視点です。
実際に、不調に陥った時に、どのような精神科医に出会うのかは、その後の職業人生における分水嶺となることが少なくありません。
ですから、人事担当者や産業医の立場では、「精神科医療機関に通っているから大丈夫」と考えるのではなく、不調を抱えている労働者が、本当に主治医を信頼し、安心して通院ができているのかにも、気を配れると良いでしょう。
本稿の冒頭に記載をした通り、誰にとっても絶対的に信頼できる完璧な医師や医療機関はありませんので、主治医選びの正解は一つではありません。この「正解は一つではない」という発想は、メンタルヘルス対策全般においても言えることです。
A社で奏功したメンタルヘルス対策が、必ずしもB社でもうまくいくわけではありません。業種や企業規模、労働者の男女比や年齢構成などの基本的な属性の違いはもちろんのこと、様々な要因で形づくられる社風や文化・慣習、そして経営理念や株主構成など、どの職場にも全く異なる個性があります。
ですから、メンタルヘルス対策においては、絶対的な正解を求めるのではなく、法令や指針等の基本を押さえた上で、常に人事担当者や産業医がリテラシーを高め、新しい情報をキャッチアップしながら、自分たちの職場を良くするであろうと思える施策についてのPDCAサイクルを回し続けることが重要なのです。
単に労働時間の削減やストレス軽減にとらわれない、自由な発想こそが、昨今の職場で喫緊の課題となっている「メンタルヘルス」の問題についてのブレイクスルーに繋がっていくのだと、私は確信しています。
.png?1763605558?w=120)







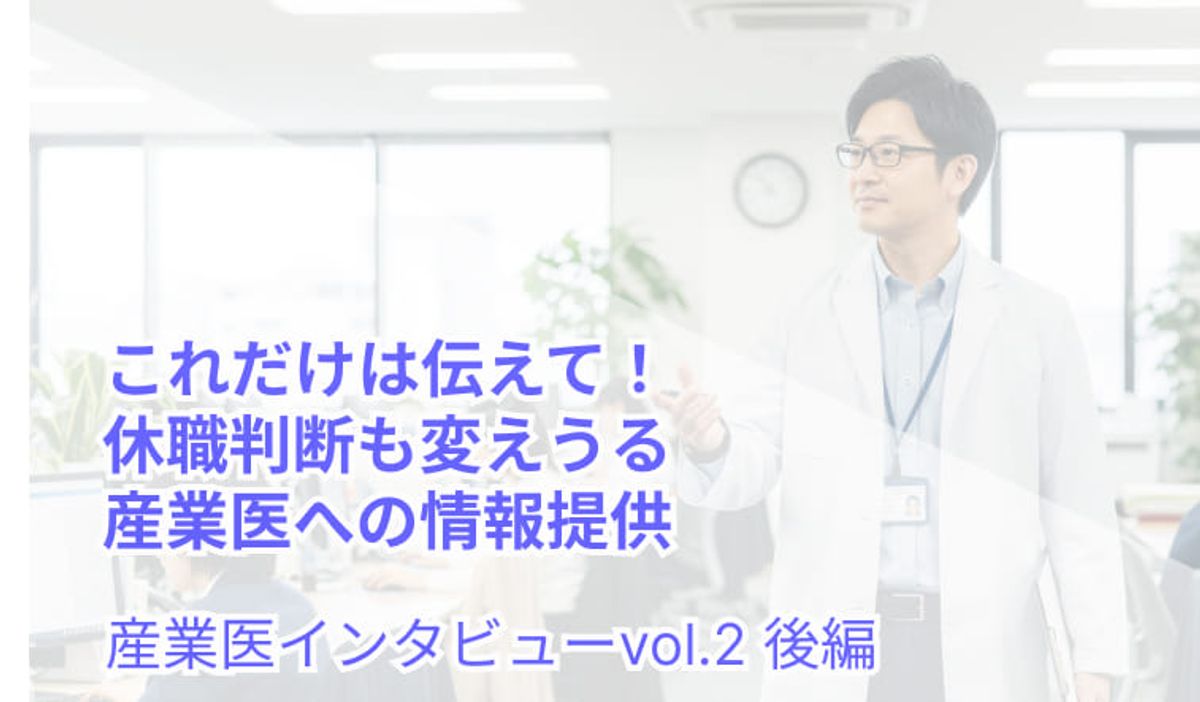
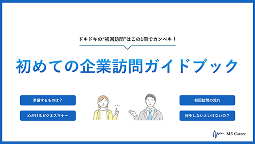
.png?1763605558?w=96)







