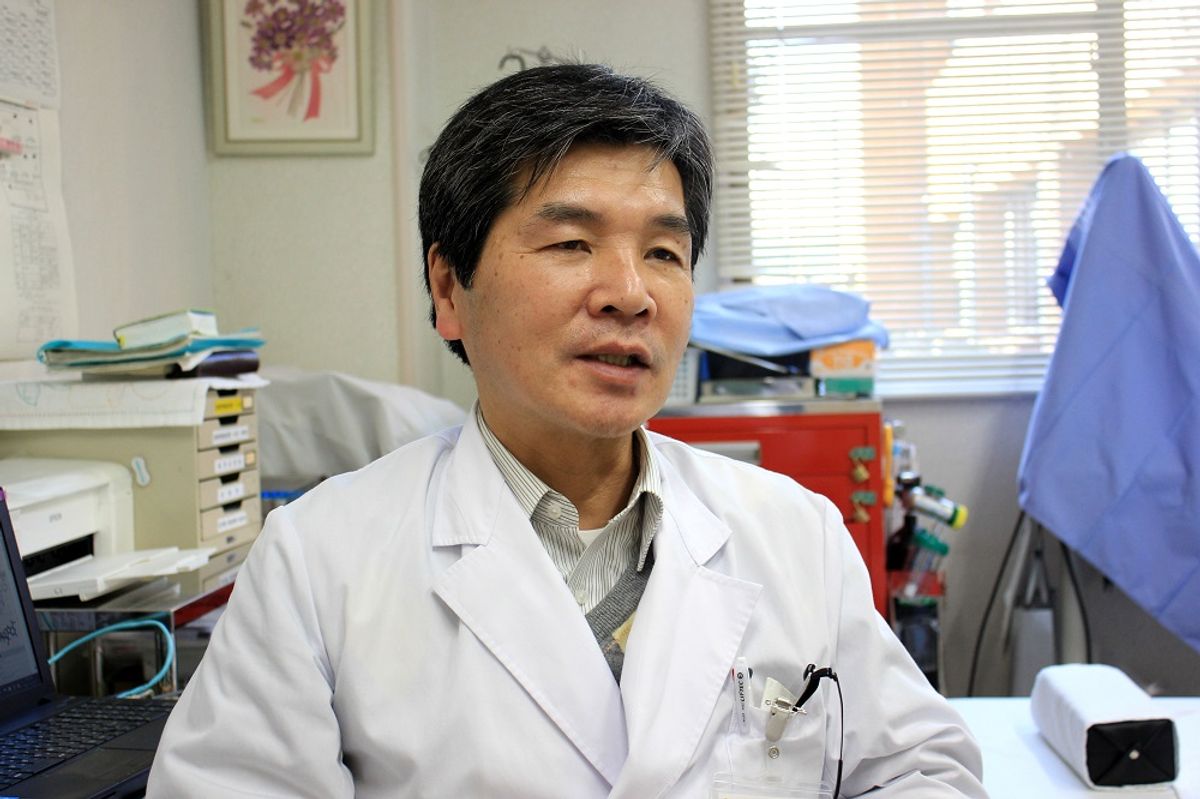
若手時代とはまた違った思いを実現できる、60代。定年をむかえ、医師として現場で活躍し続けるか、現役を退くかを選択する節目の時期とも言えます。今回取材した藤井宏二氏は2016年4月、福島県の南相馬市立小高病院に赴任。東日本大震災で医師不足が深刻化した地域の医療を守っています。京都第二赤十字病院で30余年にわたって外科医として勤務する一方、「自分の辞め時」を考えてきた藤井氏が思う、定年間際の医師のあり方とは。
65歳定年を待たず、「60歳でリタイアしよう」
―医師になられた理由と、現在までの足取りを聞かせてください。
岡山県倉敷市で代々医師の家系に育ち、自然と医学の道を志しました。1982年に関西医科大学を卒業後、大学には残らず、すぐ京都第二赤十字病院に入職。そのまま30年以上同院で勤務していましたが、2016年4月から南相馬市立小高病院に赴任しました。
― 一つの病院に長く勤められたのですね。その間、転職を考えたことはありませんでしたか?
京都第二赤十字病院は、京都市内でも症例数がトップクラスで大学病院にも引けを取りません。わたしは乳がんが専門ですが、仕事上の不自由はなく、転職は考えませんでした。ただ、研修医の頃から先輩の姿を見て「外科医は辞め時が難しい」とは感じていました。年齢とともに手元が見えにくくなると、どうしても抜糸や縫合が難しくなります。日赤病院は65歳で定年ですが、体力面も考え、「60歳くらいになったらリタイアしようかな」と若いころから考えていました。実際に60歳が迫り、さてどうしようかという時に、東日本大震災が起きたのです。
日赤病院ですから、若手医師たちはすぐに被災地に向かいました。わたしたち世代の医師は、病院にとどまって見送る側でしたが、「自分も何か力になりたい」という気持ちを押さえられませんでした。1995年の阪神大震災では、救護班の班長として震災当日に被災地に入った経験があり、東日本大震災でも支援したい気持ちが強かったんです。
被災地で見た、赤と黒のコントラスト
 ―震災がターニングポイントになったのですね。被災地のなかでも、南相馬市を選んだのはなぜだったのでしょうか?
―震災がターニングポイントになったのですね。被災地のなかでも、南相馬市を選んだのはなぜだったのでしょうか?
南相馬市は地震、津波、原発のトリプル災害で、特に被害が大きかった地域です。福島県はもともと人口に対する医師数が少なく、震災後はさらに医師が足りなくなっているのではないかという問題意識もあって2014年の秋、学会のついでにバスで南相馬市を訪れ、現地の様子に衝撃を受けました。
山の紅葉が美しい季節でした。ところが、ふと視線を下にやると大きな黒い袋が積み上げられていました。除染で出た汚染残土や廃材が入った袋が、延々と続いていたのです。紅葉の赤と、汚染残土が入った袋の黒。このコントラストが目に焼き付いて仕方ありませんでした。
その日は、南相馬市立総合病院で現地の話を聞きました。屋上に案内されて目にしたのは、広々とした太平洋。ただ、現地の方に伺うと、「もともとは防風林があって海は見えなかったのに、その防風林も津波で流されてしまった」と。帰り道には、非常に気持ちが重くなりました。この景色を見てしまったからには、来るしかない―京都に帰って家族に伝えると、「行っておいで」と言ってくれて―。こうして、単身赴任で当院に入職したのです。65歳までの3~4年間はここで医療をし、その後は京都に帰るつもりでいます。
若手にポジションを譲り、医師不足の地域で活躍する
 ―現在はどのような診療をされているのですか?
―現在はどのような診療をされているのですか?
コモンディジーズ全般です。わたしは外科医ですから、内科診療をする不安はありましたが、手に余る疾患があれば、南相馬市立総合病院に紹介するスタンスをとりつつ、一通りのコモンディジーズには対応できています。縫合など外科のスキルを生かしつつ総合診療医のような位置づけで幅広く対応していけたらと考えています。
患者は除染作業員や復興作業員が多いですね。夏場は熱中症で1日10人ほど来院することもあります。2016年夏に避難解除されてからは、地元の人も増えてきました。
 ―南相馬市立小高病院に赴任して1年が経とうとしています。今だから感じるやりがいはありますか?
―南相馬市立小高病院に赴任して1年が経とうとしています。今だから感じるやりがいはありますか?
都会のように大勢の患者は来ませんが、「医師が患者を待っている」という事実があることで、帰還する市民の皆さんに安心してもらえたらうれしいですね。わたし自身も意外だったのですが、ここにいると「自分は必要とされているんだ」と、都会の病院では味わい難いやりがいを感じます。
―今後の目標や課題を教えてください。
南相馬市は、今も医師や看護師、薬剤師、他の医療スタッフも圧倒的に足りていません。当院から薬局まで車で20分弱もかかりますから、運転ができない高齢者などは薬を処方しても受け取れない状況。そのため、テレビ診察を導入し、薬の宅配ができないか、検討しています。医薬品医療機器等法の関係をクリアできれば、そう遠くないうちに新たな試みとしてスタートさせられる予定です。
 ―最後に、セカンドキャリアを考えている医師へメッセージをお願いします。
―最後に、セカンドキャリアを考えている医師へメッセージをお願いします。
医師もある程度の年齢になれば、走るスピードが遅くなり、若い頃と同じような医療はできなくなります。都会の病院のポジションを若手に譲って、ベテランは最後の数年を医師の少ない地域で過ごすのもいいのではないでしょうか。このように考えるのは、わたしが研修医だった頃、先輩が病院を辞めたことで自分が残ることができたという経験があるからです。「きっと、あの先生は席を譲ってくれたんだろうな」と、いま振り返ると思います。転職に際して不安や葛藤もあるかもしれませんが、思い切って一歩踏み出せば、あとは弾みでなんとかなる。特に、都会の医師にそう伝えたいですね。
定年後のキャリアをお考えの先生へ

定年後はどのように働きたいとお考えですか。
先生のご懸念やご事情を伺った上で、地方の実情や待遇、サポート体制など正直にお伝えし、前向きな気持ちで次のキャリアに踏み出せるように最大限のご支援をしたいと考えております
●地域医療に貢献したい
●若手医師の育成をしたい
●体力的に無理のない範囲で働きたい
エムスリーキャリアは全国10,000以上の医療機関と提携し、先生のご希望に沿った働き方をご提案いたします。
そして専任のコンサルタントが情報収集やスケジュール調整、条件交渉などを代行いたしますので、時間的・心理的負担を軽減できます。
















.png?1730779856?w=96)

.png?1708589605?w=96)
