「労働環境改善に興味がある」「臨床現場で感じるストレスが少なさそう」など、産業医としてのキャリアに興味を持つ医師は多いようです。しかし、医師なら誰でも産業医になれるわけではなく、労働安全衛生法が定める要件のいずれかを満たさなければなりません。産業医資格を取得するために、どんな手続きが必要なのでしょうか。取得を考える前におさえるべきポイントをまとめました。
要件を満たさないと産業医になれないわけ
そもそもなぜ、産業医には一定の要件が求められるのでしょうか。産業医としての要件が定められたのは、1996年の労働安全衛生法(以下、安衛法)の改正にさかのぼります。
 歴史的に産業医は、業務に危険が伴う職場(工場や劇物を扱う作業現場など)での労働者の健康を守るため、1939年、工場法によって工場医の選任が定められたことに起源があります。工場医には結核などの感染症や、身体面の症状への対応が求められ、1972年に安衛法で「産業医」という名称が定められた当初も、医師であれば誰でも産業医として働くことが可能でした。
歴史的に産業医は、業務に危険が伴う職場(工場や劇物を扱う作業現場など)での労働者の健康を守るため、1939年、工場法によって工場医の選任が定められたことに起源があります。工場医には結核などの感染症や、身体面の症状への対応が求められ、1972年に安衛法で「産業医」という名称が定められた当初も、医師であれば誰でも産業医として働くことが可能でした。
しかし、社会の労働環境の変化に伴い、産業医の業務内容も変化しました。職場環境へのストレスを抱える労働者や、脳・心臓疾患などにつながる所見を有する労働者の増加などを背景に、産業医には労働衛生にかかわる専門知識などが求められることから、1996年、一定の要件を満たす医師でなければ産業医になれないとする安衛法の改正が行われました。
産業医に必要な要件とは?
では、具体的にどんな要件を満たさなければならないのでしょうか。安衛法第13条第2項では、下記のように示しています。

今回は、これから産業医資格を取得しようと考えている医師のルートとして一般的な(1)研修を受けて産業医資格を取得する場合、(3)労働衛生コンサルタント試験に合格して産業医になる場合について、解説します。
日本医師会の研修を受けて産業医になる
日本医師会では、所定のカリキュラムに基づく産業医学基礎研修を50単位以上修了した医師、またはそれと同等以上の研修を修了したと認められる医師を「日本医師会認定産業医」として認めています。厚生労働省が発表した「産業医・産業医科大学のあり方に関する検討会報告書」(2007年)によると、日本医師会認定産業医は7万922人、産業医科大学産業医学基本講座修了者は1935人となっており、多くの医師が日本医師会を通じて認定産業医となっていることが分かります。
研修は1単位1時間とされ、各地の医師会などが主催しています。基礎研修の構成は、
- 前期研修(14単位以上)…総論、健康管理、メンタルヘルス対策など
- 実地研修(10単位以上)…職場巡視などの実地研修、作業環境測定実習など
- 後期研修(26単位)…地域の特性を考慮した実務的、やや専門的、総括的な研修
となっています。
なお、研修を受けて交付された認定証の有効期限は5年間となっています。この有効期間の間に、産業医学生涯研修を20単位以上修了しないと資格の更新ができず、認定が喪失されてしまいます。
更新に必要な研修は、
- 更新研修(1単位以上)…労働衛生関連法規と関連通達の改正点などの研修
- 実地研修(1単位以上)…職場巡視などの実地研修、作業環境測定実習などの実務的研修
- 専門研修(1単位以上)…地域特性を考慮した実務的・専門的・総合的な研修
となっています。
このように、「日本医師会認定産業医」を維持する場合には定期的な更新が必要となりますが、地元の医師会とのつながりが得られ、さまざまな情報が得られるなどのメリットがあります。
産業医科大学の産業医学基本講座を受けて産業医になる
産業医科大学の産業医学基本講座を受講することでも、産業医の要件を満たすことは可能です。例年、産業医学基本講座は年1回、4月から約2か月間にわたって開講され、産業医学に関する実践的な講義や、グループに分かれての演習、作業環境実習などが行われます。
産業医科大学以外を卒業した医師にも、受講の門戸は広げられており、全授業科目の履修認定を受けた場合、産業医学基本講座修了認定書(産業医科大学産業医学ディプロマ)が授与されます。
労働衛生コンサルタントに合格して産業医になる
上記のように、多くの医師が研修を通じて産業医となりますが、そのほか労働衛生コンサルタント(保健衛生区分)の資格を取得した場合にも、産業医としての要件を満たすことができます。
労働衛生コンサルタントは、事業所における労働安全または労働衛生の水準の向上を図るため、事業者からの依頼を受けて事業所の診断や、これに基づく指導を行う資格で、医師免許保有者であれば、受験資格が認められます。産業医になった後に労働衛生コンサルタントとしての資格を取り、キャリアの幅を広げるというケースも多いようです。
試験は筆記試験、口述試験によって行われ、合格率は例年およそ30%となっています。筆記試験は通常、▽労働衛生一般(択一式)▽労働衛生関係法令(択一式)▽健康管理(記述式))の筆記試験―の3科目となりますが、医師は科目免除の対象となっており、労働衛生関係法令だけを受ければ良いということになっています。また、日本医師会の「産業医学講習会」、産業医科大学の「産業医学基本講座」を修了した場合は、筆記試験の全科目の免除を受けることができます。

まとめ
労働環境の変化とともに、産業医にも独自の専門性が求められるようになりました。所定の研修など、産業医になるための要件が設けられているのは、社会的な期待、必要性が高まっているということの裏返しとも考えられます。将来を見通しながら現在の時間的余裕に合わせて、資格取得のタイミングを検討することが、キャリア形成のための第一歩となります。
産業医としてのキャリアをご検討中の先生へ

エムスリーキャリアでは産業医専門の部署も設けて、産業医サービスを提供しています。
「産業医の実務経験がない」
「常勤で産業医をやりながら臨床の外勤をしたい」
「キャリアチェンジをしたいが、企業で働くイメージが持てない」
など、産業医として働くことに、不安や悩みをお持ちの先生もいらっしゃるかもしれません。
エムスリーキャリアには、企業への転職に精通したコンサルタントも在籍しています。企業で働くことのメリットやデメリットをしっかりお伝えし、先生がより良いキャリアを選択できるよう、多面的にサポートいたします。
.png?1763605558?w=120)








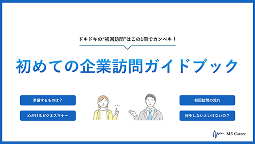
.png?1763605558?w=96)







